
皆さん、こんにちは!
富士通ラーニングメディア ナレッジサービス事業本部の吉田です。
私は、プロマネ品質上流チームに所属し、日々プロジェクトマネジメントの知識習得に奮闘中です。
このコラムは、プロジェクトマネジメントや品質マネジメント、上流工程について執筆するシリーズの第6弾です。
今回は、プロジェクト成功の鍵を握る「計画」の重要性について語っていきます。
皆さんのプロジェクトは、いつも計画通りに進んでいますか?
私の経験から言っても、計画通りに進むプロジェクトは、本当に稀だと思います。多くのプロジェクトが、計画の甘さからくる遅延、コスト超過、品質問題に苦しんでいます。
そう、プロジェクトの成否は「計画の質」に大きく依存すると言っても過言ではないのです!
とはいえ、プロジェクトの計画においては、私も含めて、皆さんも色々とお困りの部分が多いのではないでしょうか?
例えば、多くのプロジェクトが直面する「計画通りに進まない!」という問題。これは、様々なことが原因にあります。綿密な計画を立てていない、つまり、計画を軽視していることや、計画したつもりになっていることが考えられます。
さらに、「しっかり計画したのに・・・!」という声もよく耳にします。果たして、「しっかり」した計画とは何でしょうか?
私もかつてプロジェクトマネージャーとして進めていたプロジェクトでも、計画通りに進まず、プロジェクト遂行中に何度も起動修正しました。
そうなると、「どうせ計画通りに進まないなら、プロジェクト実行中に起動修正すればいいのでは?」という話も聴きますが、そもそも綿密な計画を立てていなければ、起動修正も正しくできません。
プロジェクトを進めていくうえで、計画はプロジェクトをゴールに導く重要な役割を果たします。そして、計画の不備は多くの問題を招きます。計画が綿密でなければ、プロジェクトは多くの問題を招き、最終的には失敗してしまうのです。
では、プロジェクトを成功に導く「計画」とは何でしょうか?
そして、計画の不備・・・つまり、計画に欠陥がある状態。それがあると、どんな問題が起きるのでしょうか?
まず、計画の不備が招く問題は多岐に渡ります。例えば、下記のようなものです。
これらの問題は相互に関連し合い、悪循環を生み出す可能性があります。
例えば、計画段階でコストの見積り不足があると、必要な人員や資材が不足します。そのため、納期に間に合わせるために残業が増え、質の低い作業をせざるを得なくなります。すると、納期はさらに遅れ、メンバーは疲弊し、モチベーションが下がり、さらに作業効率が低下します。結果、プロジェクト全体が失敗する可能性が高まる、という悪循環になります。そのため、綿密な計画とリスク管理が不可欠なのです。
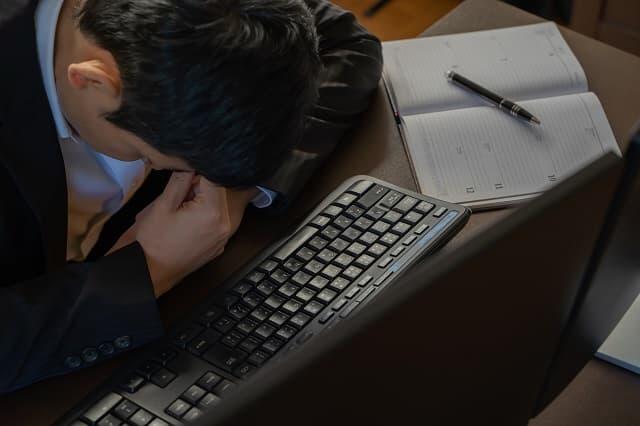
さて、計画の不備が様々な問題を招くことが分かりました。そうなると、ますます綿密に計画するとは何か、知りたくなりますね。
では、何度も登場している「綿密な計画」ついて掘り下げてみましょう。
綿密な計画と聞くと、まだ始まってないプロジェクトを計画段階で細部にまでスケジュールに反映させる必要があるように感じる方もいると思います。確かに、スケジュールは詳細で抜け漏れないものを作らなければ、上記で紹介したような計画の不備を招き、問題が多発する可能性があります。
では、「綿密な計画」はどのように作っていくのでしょうか?
まずは、質問です。
皆さんは、プロジェクト計画時に、イチからスケジュールを作成しますか?
私は同じようなプロジェクトのスケジュールを参考にして作成しました。おそらく、皆さんの会社にも、様々なプロジェクトの資産が存在していると思います。
参考になる他プロジェクトのスケジュールを活用することは、とても有効なことです。また、PMBOK(R)ガイドなどの標準的なプロジェクトマネジメント知識を参考に、抜け漏れのない計画を作成することも大事です。例えば、PMBOK(R)ガイドでは、スコープ、スケジュール、コスト、リスク、品質、リソース、コミュニケーション、ステークホルダーなど、様々な項目について計画を立てることが推奨されています。これらの項目を網羅的に検討することで、より現実的で、リスクに強い計画を策定できます。
上記をもとにスケジュールを作成しても、まだ曖昧な部分があると思います。その曖昧な部分こそ、リスクとして認識し、事前に対策を立てておく必要があります。「いま、明確になってないことは何か?」「いつ、誰が明確にできるのか?」「このリスクが発生した場合、どのように対処するのか?」といった点を具体的に検討し、計画に反映させることが重要です。
大事なことは、目の前の状況だけでなく、未来の可能性も考慮し、リスクを管理しながら、目標達成のための道筋を明確に示すことです。見える化されていない潜在的な問題まで見据えた計画こそが、プロジェクト成功への鍵です。
しかし、こんな疑問もあります。
「色々な資料を参考にすることは既にやっている。それでも、プロジェクト開始前から抜け漏れない完璧な計画なんてできない。一体、どうすればいいの?」
確かに、計画段階で詳細な抜け漏れない計画を作成するのは相当難しいです。プロジェクトは一つとして同じものはないです。そのため、社内の似たようなプロジェクトを参考にしても、PMBOK(R)ガイドを参考にしても、自分のプロジェクトにとって完璧な計画なんて、プロジェクト開始前にはできない、そもそも完璧な計画なんて出来るの?と思ってしまいますね。
私も、自分がプロジェクトマネージャーだった際に、計画の難しさについてはすごく悩みました。
計画時点では最大限必要なことは考えているのに、スケジュールの遅延が起こると「ちゃんと計画していたの?」と言われてしまう。私のようなモヤモヤを感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのモヤモヤを解くポイントは、計画の段階的詳細化です。
結論から言うと、完璧な計画=最初から詳細で抜け漏れない計画を目指すことはとても難しいです。それよりも、段階的詳細化で進める計画=十分な計画を目指すことこそが重要なのです。
プロジェクトを進める上で、計画に必要以上の時間を費やすことは、かえって非効率的な場合があります。完璧な計画を目指し、細部まで徹底的に詰め込むよりも、必要な情報を、必要な時に、必要なだけ準備することが重要なのです。
これは、計画の初期段階では、全体像を捉え、主要なマイルストーンとタスクを明確にすることに集中し、詳細な情報は必要に応じて段階的に詰めていくアプローチをします。計画から得られる情報は、次のステップへ進むために「十分」であれば良いのです。必要以上に詳細な計画は、変化への対応を困難にし、柔軟性を失わせる可能性があります。
例えば、冬の北海道旅行を例に考えてみましょう。
旅行の計画を立てる時、行きたい場所は決めておく必要はありますが、天気予報や現地の積雪状況、混雑状況などは、旅行直前あるいは現地に行かないと分かりません。そのため、計画段階では分刻みの予定を決める必要はないですよね。行きたい場所の大まかなリストを作成し、旅程の概要を決めてしまえば十分です。
旅行計画も「段階的詳細化」です。完璧な計画を目指さず、必要十分な情報で始め、状況に応じて柔軟に修正していくことで、思わぬトラブルにも対応でき、より楽しい旅になります。まあ、旅行の場合は予定通りにいかないこと自体を楽しむ余裕も、計画の重要な要素かもしれませんね。
このように、段階的詳細化によって、計画の柔軟性を維持し、変化に迅速に対応することができます。計画は「完璧」を目指すのではなく、「十分」であることを目指すことで、プロジェクトの成功確率を高めることができるのです。 大切なのは、計画を「生きているもの」として捉え、状況に合わせて適宜修正していく柔軟性を持つことです。

計画段階で「十分」な計画を目指すことが重要だとわかったと思います。
よく耳にする「計画は綿密に立てること」は、計画段階で細部にわたり抜け漏れなく完璧な計画のことではなく、本来、段階的詳細化で柔軟性がある生きた計画のことを指しています。皆さんの会社でも「詳細で完璧な計画」の方に、縛られ過ぎている場合もあるのではないでしょうか。
では、振り返りです。
プロジェクト成功の鍵は「計画の質」。プロジェクト計画における「十分な計画」は、計画段階で全体像を捉え、主要なマイルストーンとタスクを明確に、潜在的なリスクや問題点を洗い出すことです。プロジェクトの資産やPMBOK(R)ガイドなどを参考に、スコープ、スケジュール、コスト、品質などを網羅的に計画するのが、プロジェクトマネージャーの役割です。
計画段階で完璧な計画は不可能ですが、段階的詳細化で柔軟性を確保し、変化に対応した計画を作成します。関係者全員が共有・合意する「生きた計画」を目指し、具体的な行動指針、リスク対応策、進捗状況の可視化を盛り込むことが大事です。計画は単なる準備作業ではなく、成功への確実な道標です。
「計画」の重要性を軽視することは、プロジェクトの失敗リスクを高めるのです。

さて、プロジェクトの計画が重要であることをお伝えしてきました。皆さんに、プロジェクト計画を学ぶおすすめの研修をご紹介します。
コース名は、「プロジェクト計画」です。PMBOK(R)ガイドにある5つのプロセス群(立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)において、特に計画プロセス群を丁寧に説明しています。PMBOK(R)ガイドに基づき、具体的な手順や手法、ツール、テンプレート例を示しながら、プロジェクトの成功に向けた計画の重要性を強調しています。
具体的には、WBSの作成と様々な見積もり手法について、これらをマスターすることで、より正確なスケジュールとコストの見積もり、そして資源の最適化が可能になります。さらに、リスクマネジメントについても深く掘り下げており、リスクを事前に特定し、分析、評価することで、適切な対応策を講じることができ、プロジェクトの失敗を未然に防ぐことができます。
この研修で学んだことを実践することで、プロジェクトマネジメントスキルを大きく向上させることができます。プロジェクトマネージャーとして、計画を立て、リスクを最小限に抑えながら、プロジェクトをスムーズに進めることができるようになります。
プロジェクトマネジメント手法として、注目されているアジャイル開発においても、計画は必要不可欠です。ただし、ウォーターフォール型とは違い、イテレーション(反復開発)ごとに計画を立て、柔軟に修正していく点が異なります。
本研修はウォーターフォール開発での計画を主に解説していますが、アジャイル開発における計画についても、この研修で学んだ基本的な考え方を応用することで、より効果的な計画立案が可能になります。
・【集合】プロジェクト計画(UAR12L)
同等の内容で、ライブ研修(オンライン)やe講義動画もあります。
富士通ラーニングメディアでは、システム開発に関わる方に対する初心者向けのプロジェクトマネジメント基礎研修から、経験者向けの応用研修まで、幅広いニーズに対応した研修プログラムをご用意しています。また、初めてマネジメントを学ぶ方向けのコースも用意しています。
プロジェクトマネジメントの知識を身につけたい方は、ぜひ富士通ラーニングメディアの研修をご検討ください。
(注1)これまで私が執筆したプロジェクトマネジメントや品質マネジメント、上流工程(要件定義)におけるコラムも是非ご覧ください。
これからも皆さんにとって有益な情報をお届けできるよう尽力します。今後のコラムも是非楽しみにしてください。

ナレッジサービス事業本部 プロマネ品質上流チーム所属
吉田 千鶴(よしだ ちづる)
COBOLやメインフレームの研修講師を経て、近年はアジャイル研修の講師やシステム開発のプロマネも経験しています。美味しいコーヒーを飲みながらまったりする時間が好きです。
(2025/02/27)