
11月14日、弊社は、東京コンファレンスセンター品川において「人材育成セミナー2019」を開催しました。人材育成に興味を持つ企業経営者や、経営企画/人事/人材開発/DX推進/情報システム部門の責任者の方々を対象にした同セミナーは、今年で6回目を迎えます。今回は、「個と組織のエンゲージメントを高める人材育成を考える」をテーマに掲げました。人と人とのつながりを活性化させ、人材育成を強化していくためには何をすべきなのか――。セミナーでは日本ダンス界の第一人者である夏まゆみ氏の基調講演をはじめ、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏による特別講演、さらには、弊社のお客様で、積極的に人材育成に取り組んでいる企業・団体の事例の講演が行われました。
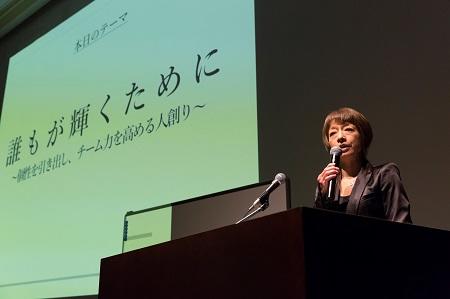
最初に登壇したのは、ダンスプロデューサーの夏まゆみ氏です。夏氏は「AKB48」や「モーニング娘。」をはじめ、これまで300組以上のアーティストの振り付けを担当してきました。
夏氏の講演テーマは、「誰もが輝くために ~個性を引き出し、チーム力を高める人創り~」です。メンバーひとりひとりの個性を引き出し、どのように鼓舞していくのか。夏氏は、「指導する際に意識しているのは、相手との『関係づくり』と能力を存分に発揮させる『環境づくり』です」と説明します。
「関係づくり」は相手と同じ目線に立ち、人間として対等な関係を構築すること。そして「環境づくり」は「結果ではなく取り組む姿勢を評価して褒める」ことが大切だといいます。
「指導する立場の人は、言葉の使い方に意識を向けてほしい。上司が叱る目的は、気付きを与え、相手の成長を促すためです。否定形の叱咤で萎縮させるのではなく、ポジティブな言葉で、相手に自信とやる気を与えるようにすること。そして、複数の部下を統括する立場でも、必ず1対1で相手に向き合うこと。『1対多』ではなく『1対1』の関係が人数分あると考えてください」(夏氏)
こうして成長したメンバーが、それぞれのポジションで能力と魅力を最大限に発揮することで、最強のチームが生まれます。夏氏は「企業に置き換えれば、社員ひとりひとりが自らの役割に責任を持って(担当職務の)リーダーとなり、目的を明確に共有することです」と訴えました。
続くセッションでは、弊社のお客様が登壇。現在、積極的に取り組んでいる人材育成の事例をリレー形式でご紹介いただきました。

最初に登壇したのは、茨城県産業技術イノベーションセンターでセンター長を務める大力賢次氏です。茨城県では、新しい豊かさを目指し、先端技術を取り入れた新産業の育成に取り組んでいます。その中で同センターは、県内産業の発展を目指し、技術開発やイノベーション創出を支援する役割を担っています。
現在、同センターが「次世代技術活用ビジネスイノベーション創出事業」として注力しているのが、IoT(Internet of Things)や人工知能(AI)を活用したビジネスモデルの構築です。その一環として富士通ラーニングメディアと共に実施しているのが「IoT・AI人材育成講座」です。また、同講座で学んだ知識を実現するために「AIビジネスモデル研究会」の運営や,ビジネスモデル構築研修を実施し、新ビジネス創出とそのために必要な人材育成に取り組んでいます。
大力氏は、これらの活動内容を説明するとともに、「来場した企業の皆様とのエンゲージにより、人材育成とビジネス創出の共創など、更にステップアップを目指したい」と、その展望を語りました。

続いて登壇した第一生命情報システム(DLS)で経営企画部 人財開発グループ長を務める元尾しのぶ氏は、富士通ラーニングメディアと共同で実施している「人財育成サイクル」や、「学びから実務までの段階的な人財育成」について紹介しました。
DLSではデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応できる「モード2人財」の育成を積極的に進めています。これはDLSのCDP(キャリア開発プログラム)に基づく研修体系を拡充したもので、「DX人財(モード2人財)」の育成も目指しながら、(従来の)人財育成プロセスの改善と効率化を図る取り組みです。
「学びから実務までの段階的な人財育成」は、DX分野で活躍が期待できる社員に対し、段階的な育成の道筋を策定して成長の機会を提供する取り組みです。講演ではこれら取り組みの成果や、実際のビジネス創出事例などが紹介されました。

全社員にデータサイエンスの研修を実施している事例を紹介したのが、ダイキン情報システムです。同社は2015年4月に、先進IT技術に基づいて業務改革を推進し、全社に対して価値創造を提供していくことをミッションとした「IT創発グループ」を設立しました。
セッションではIT創発グループ課長の成竹剛氏が、データサイエンス研修の内容を紹介しました。同社では富士通ラーニングメディアの教育プログラムをカスタマイズし、テーマや受講者のレベルに応じてデータ分析手法や機械学習概要の研修を進めています。また、「データ分析の内製化」を実現するため、Microsoft AzureやPythonを用いたデータ分析も実践しています。
成竹氏は、「今後の課題は、従業員に“DXマインド”を醸成することです」と語ります。そのためにはIT創発グループがエバンジェリストとなり、教育の提案実施や組織の見直しも視野に入れ、DXマインドの醸成に努めていく計画を進めています。

リレートークの最後に登壇したのが、リコージャパン ICT事業本部ICT技術本部SE統括室 CCS推進グループリーダーの古島勝一氏です。セッションでは、新しいことに対して自発的にチャレンジするシステムエンジニアを支援する「チャレンジファンド制度」を中心に、同社の取り組みを紹介しました。
チャレンジファンド制度は、システムエンジニアのアイディアを形にし、顧客との協創を通じてアイディアの有用性やビジネスとしての価値を検証することを目的としたものです。古島氏は「チャレンジファンドによって、システムエンジニアのマインドやモチベーションが高まり、DXに対して積極的に取り組む組織風土が醸成されました」と説明します。
また、2019年10月から「DX(CCS)人材研修プログラム」として、アジャイル思考やデザイン思考を学ぶカリキュラムもスタートしました。これは、技術的な学びよりも、ビジネス創造の観点を養うことを重視しているといいます。
リコージャパンでは今後もDX人材の育成に取り組み、ビジネス環境の変化にいち早く対応していく体制を構築していくとしています。
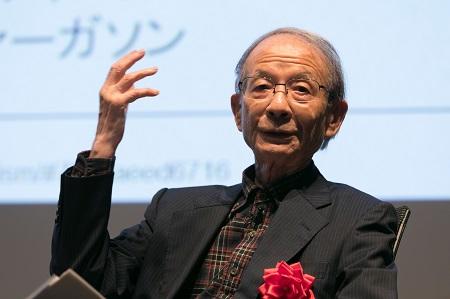
セミナーの最後は、一橋大学の名誉教授 野中郁次郎氏の特別講演です。「知識創造を促進するこれからの個と組織のあり方」をテーマに、多様な個と組織が共に高め合う組織戦略について、知識創造の視点から講演されました。
野中氏は「知識創造のプロセスを重要視する経営者は、分析・計画偏重を脱し、変化のただなかで判断して組織を導く実践知のリーダーたれ」とエールを送ります。共感と対話によって個々の社員が持つ感情や感性といった “人間力”を引き出し、実践を促す物語を紡いで社員を動かし、集合知を創造するのが実践知のリーダーです。野中氏は、暗黙知と形式知の相互変換という知識創造プロセスを機動的に推進する実践的知恵をもっている日本企業の経営者やその経営のありかたを紹介しながら、「株主価値の最大化」という経営の考え方に疑問を呈しました。
また、野中氏は、人と人との関係性では『共感』することが重要だと説きました。
「相手の視点に立って『体験』を共有しながら自分の考えや思いを徹底的に語り合い、1つの答え、つまり新しい意味に共に到達すること。この『知的コンバット』を繰り返すことで、一体感のある組織が生まれ、イノベーションが起きるのです」(野中氏)
* * *
セミナーの最後には懇親会が催されました。人材育成には「知識」と「体験」を共有し、相手と共感することが重要です。野中氏のことばどおり、参加者の皆さんは積極的に「知的コンバット」を繰り広げ、「個と組織のエンゲージメントを高める人材育成」について理解を深めました。

(2019/12/04)