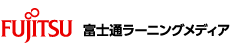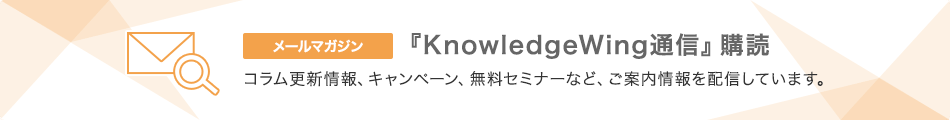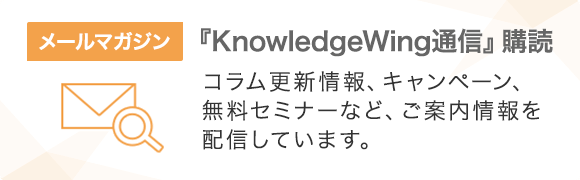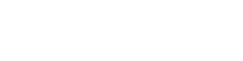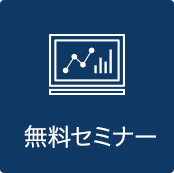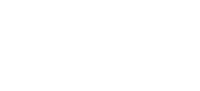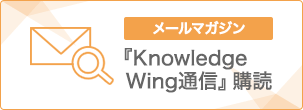みなさん、こんにちは!富士通ラーニングメディアの五十嵐です。
主に、研修の企画・設計を担当しています。
私は、2011年に半年間、インターンシップでイギリスのグローバル企業(Z社)に所属しました。
帰国後、私は、このインターンシップ経験で得たことを業務に活かしたいという想いから、当社の活動の1つである「プロジェクトマネージャの研修における評価とフィードバック」に取り組みました。
今月は、この取り組みから得た気づきについてお伝えしてきました(毎週木曜日掲載)。
本取り組みの成果を論文にまとめ、10月3日から5日にハワイで開催されたProMAC(プロジェクトマネジメント学会が主催するプロジェクトマネジメントに関する国際アカデミックカンファレンス)にて発表しました。
そこで、最終回の今回は、学会報告と、学会発表や参加者との交流によって得た気づきについてお届けします。
<ProMACとは?>
ProMACは、プロジェクトマネジメント学会主催の国際会議です。
本年度で6回目となる今大会は、10月3日から5日まで、米国ハワイにて開催されました。
ProMACは、地域、国境、業界、組織を越えて、オープンなプロジェクトマネジメントの知見、経験、成果を共有する国際交流の場です。
今大会では、世界各国から200名以上が参加し、5件の基調講演と約130件の発表が行われました。
IT企業および大学関係者が多く参加しており、プロジェクトマネジメントの実務と学術面の両面において、インターナショナルな動向を把握できる非常に有意義な機会となっています。

<国際学会の雰囲気>
開会式の後、各発表のセッションが行われました。
セッションはいくつかのカテゴリごとに分けられ、同時に進められます。
「研修と教育」「プロジェクトマネジメント知識領域」「プロジェクトへの新しい挑戦」「政府、社会、経済の変革」「ビジネス・産業への適用」「国際的なコラボレーション」といったカテゴリです。
発表時間は20分間であり、15分間はプレゼンテーション、5分間は質疑応答となっています。
私の発表は「研修と教育」カテゴリの中で行われいました。
プロジェクトマネジメント教育に関心のある方が、多数聴講していました。
質疑応答では、「なぜリスクに注目したのか?」「個人にフォーカスをあて、フォローすることに着目したきっかけは何か?」などの質問をいただき、ディスカッションをすることができました。
また、カテゴリの発表が終了した後は、他の発表者や聴講者と、あいさつや、プロジェクトマネジメントの教育に関する議論をさらに深めることができ、非常に有意義な機会となりました。
学会2日目の夜に行われた学会参加者のためのディナーでは、一堂に集まった参加者と親睦を深めることができました。

<学会発表で得たもの>
私はこの学会発表にあたり、アカデミックな論文の書き方をはじめ、仮説を設定・検証し、研究を進めていく方法などの手法を修得することができました。
加えて、今回発表を行ったことにより、大きな収穫だと感じたのは、下記の2点です。
1.本取り組み(研究)が国際的に見ても重要な観点であることを確認できた
発表後に、他の発表者や聴講者とのディスカッションにより、プロジェクトマネジメントの評価の難しさや課題を共有し、自分の取り組みの観点に納得の声やフィードバックをいただくことができました。
その結果、本取り組みが国際的にも関心が高く、重要な観点であることに気付くことができました。
国際的な学会で発表をしたからこそ、このような気づきが得られたのだと思います。
2.真のプロジェクトマネジメントのリーダーは、「熱い想い」を持っている、ということに気づいた
本学会の参加者には、大規模プロジェクトのマネージャを実践の場で担当している人がいます。
発表後の質疑応答や学会参加者とのディナーなどで、そのような経験豊富な方々とじっくり話をすることができたことも、貴重な機会でした。
その中でも、プロジェクトマネジメントの話をしていたつもりが、「日々大事にしていること」、「人をハッピーにするために実現したいこと」といったような、パーソナル面の核となる話につながり、非常に感銘を受けました。
テクニカルの要素だけではなく、そのリーダーの「熱い想い」がプロジェクトを成功に導く、ということを感じることができました。
今後も、効果的な人材育成の実践に向けて、「熱い想い」を持って取り組みを進めていきたいと思います。

---------
4回にわたって、「研修効果を向上させる個別評価とフォローアップ」をお届けしてまいりましたが、いかがでしたか。
集合研修においても、個人にフォーカスし、フォローアップを行うことによって、各個人における研修の効果を向上させることができるということがわかりました。
みなさまが、研修の効果をより高めることをお考えの際に、ご参考にしていただけますと幸いです。
また、その実現のために、当社もみなさまの人材育成のパートナーとして、お役に立ちたいと考えています。