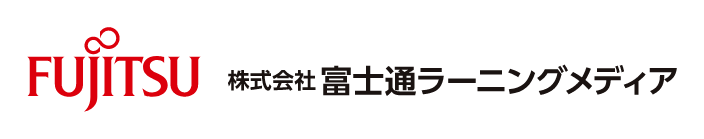- トップ
- 「ブログ」LMSラボ
- 研修で成果を上げるための事前準備と事後フォロー
- 研修
研修で成果を上げるための事前準備と事後フォロー
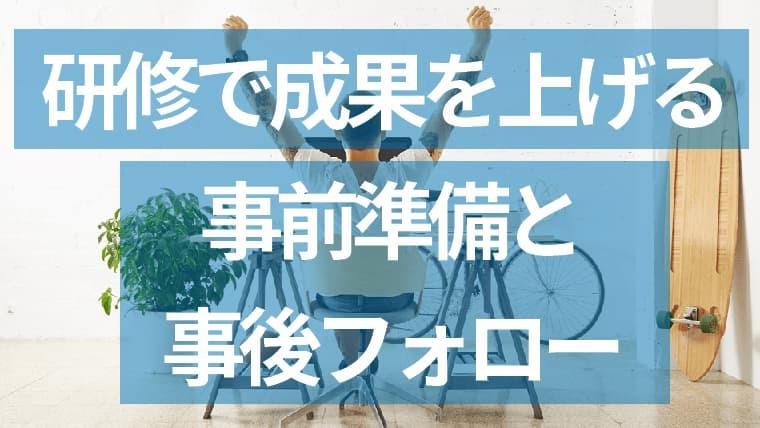
みなさまも企業の成長を目指し、社員を育てるべく、さまざまな研修を企画、実施されているのではないでしょうか。
しかし、研修を実施してもなかなか成果に繋がらない、効果があったのかわからない、という声も耳にします。
本記事では、研修の成果を上げるために理解すべき3つのポイントをご紹介します。
目次
研修の成果が上がらない3つの理由
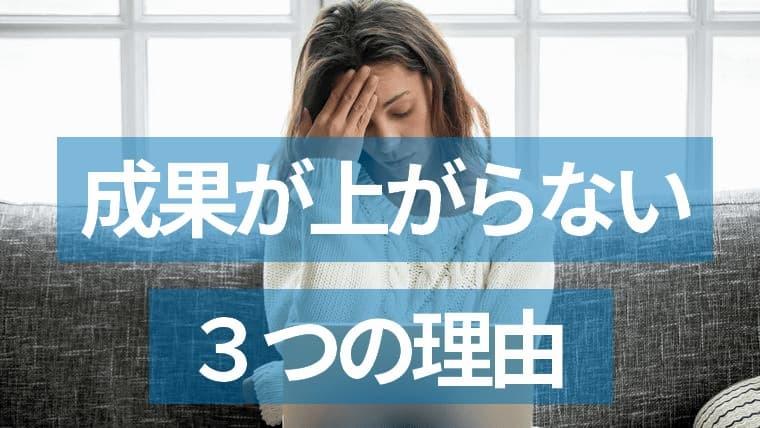
研修を実施しても成果が得られない理由として、以下の3つが考えられます。
成果が上がらない3つの理由
- 研修の目的が明確になっていない
- 受講者の当事者意識が低い
- 受講者が日々の仕事に追われてしまっている
1つずつ詳細をみていきましょう。
1.目標が明確になっていない
1つ目の理由は、研修を受講する目的が明確になっていないということが挙げられます。
研修には、受講する狙いやゴールの決定が必須です。
決定した狙いを軸として、研修での学びを活かし、どのような姿になることを受講者に期待しているのかを具体化しておくことが重要です。
例えばプレゼンテーション研修であれば、以下のような研修の目的が考えられます。
- 相手にわかりやすく伝える話し方
- 説得力のある身振り手振り
- 理解しやすい資料の作り方
ただ、研修目的があっても、受講者全員が研修後の具体的なアクションをイメージできているかというとそうとは限りません。
受講者の中には、学んだ内容を実務で活かす状況をうまくイメージできない人もいるため、研修効果が出にくい要因の1つになっています。
2.受講者の当事者意識が低い
2つ目の理由は、受講者が、当事者意識が低い状態で研修に参加しているというケースです。
企業研修の受講理由として、受講者から以下のような理由が挙げられることがあります。
- 上司からの命令
- 昇進試験のため
などです。
1つ目の理由にも関連しますが、研修を受講することで何が得られるかが明確になっていない状態で参加すると、上記のように受け身になってしまい、効果が上がらない要因になります。
3.受講者が日々の仕事に追われている
3つ目は、受講者自身は、研修での学びを業務で活かそうと思ってはいるものの、日々の仕事に追われてしまい活かせていないというケースです。
特に、受講した研修内容がヒューマンスキルなどテクニカルな内容でない場合、日々の業務に追われていると、研修で学んだ内容を意識して活かすことが難しいかもしれません。
また、研修で学んだ知識などは1週間経過すると約75%、1か月経過すると約80%忘れてしまうという研究結果があります(エビングハウスの忘却曲線)。
日々の業務を行う中で意識をして研修で学んだ内容を活かさない限り、学んだ内容を忘れていくことになるため、効果が上がらない1つの要因となっています。
研修の成果を上げるための3つの事前準備
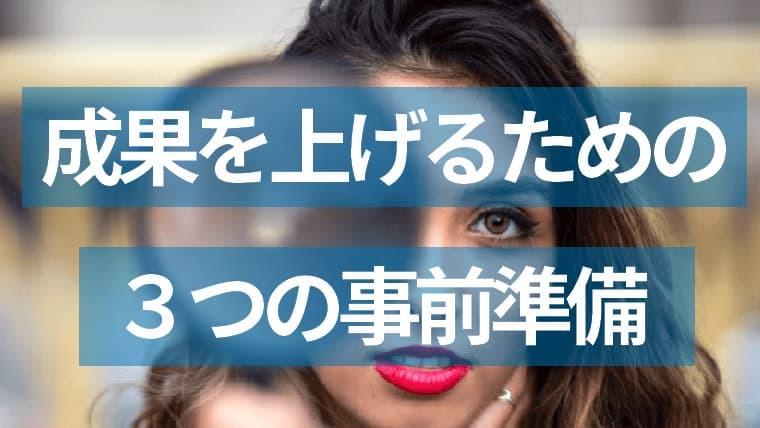
ここからは研修で学んだ内容を活かし、効果を上げる方法をご紹介します。
まず、研修受講の事前準備として確認しておくべき3点です。
研修受講の事前準備
- 研修受講後に目指す姿をあらかじめ提示する
- 研修を業務で活かすことをイメージさせる
- 研修での積極的な参加&失敗を促す
1つずつ解説していきます。
1.研修受講後に目指す姿をあらかじめ提示する
事前準備の1つ目は、「研修を受講した後、受講者にどのような状態になっていて欲しいのかをあらかじめ提示する」ことです。
研修の狙いやゴールを明確にするメリット
- 研修によって何を知って欲しいのか、受講者側が研修企画側の意図を理解できる
- 受講者が研修で何を学び、持ち帰るべきなのかが明確になる
研修で学ぶことが明らかでないままで受講すると、研修の必要性が曖昧な状態で学ぶことになり、研修の成果を持ち帰ることが難しくなります。
目標、つまり「研修によって何が得られるのかを明確にしておくこと」は、大変重要です。
2.研修を業務で活かすことをイメージさせる
事前準備の2つ目は、研修で学んだ内容を日々の業務の中で活用するシーンをイメージしてから受講するということです。
受講後に研修で学んだ内容を業務で活かそうと試みると、なかなかうまくいかない、ということがあります。
その原因は、実務での課題を意識しながら受講できていなかったからかもしれません。
組織や自分自身の課題を意識しながら受講すると、モチベーションが上がり、受講後にすぐアクションが取れるようになります。
そのため、受講者は研修受講前に、組織や自分自身の課題を洗い出しておくことが大切です。
3.研修での積極的な参加&失敗を促す
事前準備の3つ目は、研修への積極的な参加および、失敗を促すということです。
ワークショップ型や実技型などの研修で、最初からうまく出来る人は稀です。
何度もチャレンジし、失敗を繰り返すことで出来るようになります。
「研修で学んだことを、実務でやってみるとなかなかうまくいかない。」「業務で失敗することはリスクが高いため、なかなかチャンレンジしづらい。」
という経験のある方も多いのではないでしょうか。
研修中に失敗を恐れず、多くの経験を積むことが、研修受講後に実務に活かすには重要なのです。
研修の成果を定着させるための3つの事後フォロー
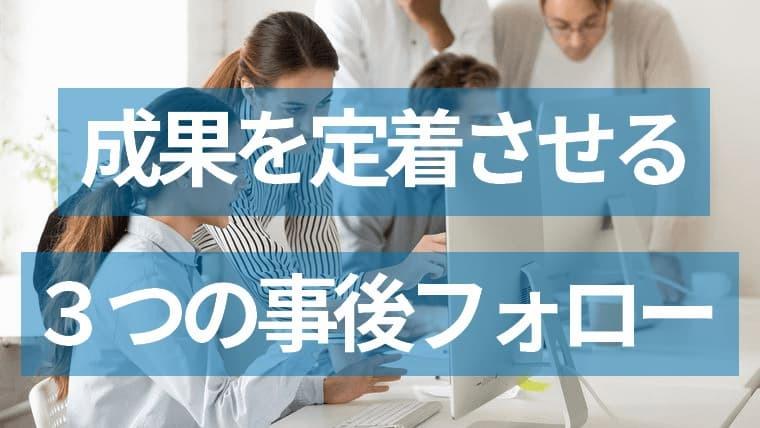
研修を受ける前の準備についてご紹介しましたが、研修で学びをたくさん得ても、受講後何もしなければそのまま忘れていってしまいます。
研修後の成果を定着化させるにはフォローアップが必要です。
おすすめのフォローアップ方法は以下の3つです。
フォローアップ方法
- 振り返りの機会を設ける
- 学んだ内容を共有する
- 研修の効果を上司が評価する
1つずつ詳細を解説します。
1.積極的に振り返りの機会を設ける
1つ目は積極的に振り返りの機会を設けることです。
日々の業務に追われていると、研修で学んだ内容を忘れやすくなります。定期的に研修で学んだ内容を振り返られる機会を、強制的にでも作ることをお勧めします。
その振り返りの中で、実際の業務で活かせたかをチェックし、改善していきます。
繰り返して振り返ることが、研修内容の定着化に繋がるため、フォローアップの大きな要素になります。
2.学んだ内容を共有する場を作る
2つ目は、受講者自身が研修で学んだ内容について、所属部署、チームメンバーへ報告・共有する場を作るということです。
研修で得た情報をアウトプットすることで、得た知識を整理をできます。メンバーへわかりやすく伝えるためには、自分自身が理解していることが不可欠です。
研修でインプットした情報をアウトプットする場を作ることで、さらに理解を深められます。
3.研修後の効果を上司が評価する
3つ目は、研修受講後の変化を上司が評価するという施策です。
受講者に、「研修を受けて一定期間経った後に、行動の変化があったかを上司が評価する」ということを事前に伝えておきます。
評価されるということを意識すると、意識的に研修の内容を業務に活かそうという姿勢が生まれます。
また、上司からメンバーへフィードバックすることも可能です。
例えば、プレゼンテーション研修の場合、
- 研修を経て資料の構成が分かりやすくなった。
- 研修直後はプレゼンテーション時に説得力のあるジェスチャーが見られたが、いつの間にかなくなっている。
というように、上司から具体的にフィードバックできます。
研修後の行動の変化を上司から評価することで、受講者の研修効果の定着に繋げることができます。
まとめ

研修の成果を上げる方法や、成果を定着化させる方法についてご紹介しました。
成果を上げるために研修コンテンツを作ることももちろん重要ですが、事前準備および、フォローアップはコンテンツ作成と同様に重要な要素です。
研修を企画、立案する際には、本記事で紹介したポイントを押さえ、自社の形態や文化にあわせてアレンジしながら進めてみてください。