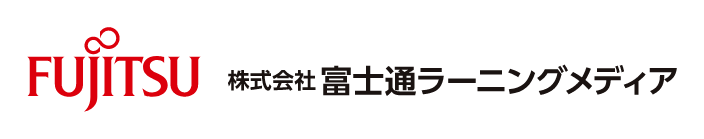- トップ
- 「ブログ」LMSラボ
- eラーニングのメリットとデメリットを徹底解説
- eラーニング
eラーニングのメリットとデメリットを徹底解説

eラーニングを活用するメリットとは何でしょうか。
このような課題はありませんか
- 自社のeラーニング導入に向けてメリット・デメリットを整理したい。
- 受講する側は、eラーニングだと何か良いことはあるの?
eラーニングの導入メリットは、運営する企業側だけではなく、受講者側にも数多くあります。
一方で、eラーニングのデメリットを事前に把握しておくことで、目的に応じた使い分けや、学習効果を高めるための準備を進めることができます。
本記事では、大企業から個人まで52万人以上にeラーニングを提供してきた富士通ラーニングメディアが、eラーニングのメリットとデメリットを解説します。
目次
eラーニングのメリット

ここでは、eラーニングのメリットをご紹介します。eラーニングのメリットは、運営する企業側にも受講者側にもあります。
| 運営側のメリット | 受講側のメリット |
|---|---|
|
|
まずは、運営側のメリットをご紹介していきます。
eラーニング運営側のメリット

eラーニングを運営する側のメリットは、以下の5つが挙げられます。
運営側のメリット
- 研修コスト削減
- 学習機会を平等に提供できる
- 学習履歴や成績が管理できる
- 教材の更新や転用が簡単
- 受講者ごとのプログラム構築がしやすい
それでは、1つずつ見ていきましょう。
運営側のメリット(1)研修コスト削減

1つめは、研修コストの削減です。具体的には、集合研修をする場合に発生する以下のコストが、eラーニングでは発生しません。
集合研修で発生するコスト例
- 受講者を同一の会場に集める交通費
- 研修を実施する会場費
- テキストの印刷費用
- テキストの配布費用
- 同じ研修内容でも会場ごとに発生する講師の費用
この他、研修のために人を集めた際に飲み物や昼食代がかかる企業もあるかもしれません。
eラーニングで研修を実施することで、会場にかかる費用や講座のテキストの配布にかかる手間や費用を削減することができます。
また、同じ研修を違う地域で実施する場合、集合研修は実施回数分の費用が発生しますが、eラーニングであれば講座を1回作成すれば場所に関係なく繰り返し活用できます。
さらに毎年同じ講座を実施する場合、過去作成したものを使うことも可能です。
運営側のメリット(2)学習機会を平等に提供できる

2つめの運営側のメリットとして、学習機会を平等に提供できるということが挙げられます。
組織全体の知識を底上げするためにも、企業にとって受講者に均等に学習機会を提供することは、大変重要です。
会場や受講日によって受講者の理解した深度が異なってしまうと、ムラのある研修を提供したことになってしまいます。
結果的に、次回以降の研修を一番理解度が低いところにあわせて続けるか、他の受講者と同じ理解度になってもらうための自習を促す、といった対応をすることになります。
受講者が研修の運営側に対する不満を抱くきっかけになってしまいますので、eラーニングが学習機会を均等に提供できることは、大きなメリットと言えます。
運営側のメリット(3)学習履歴や成績が管理できる
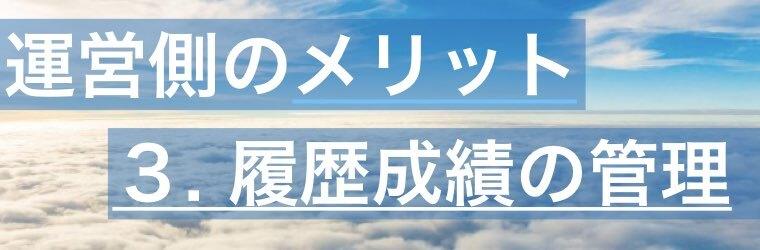
運営側の3つめのメリットとして、学習履歴や成績が管理できることが挙げられます。
eラーニングの場合、受講者の行動履歴を全てデータで記録しておくことができます。
運営側は誰がいつ何を学習したのか、講座内にあるテストの成績をデータベース化して管理することができます。
企業がeラーニングを運営する場合、LMS(ラーニング・マネジメント・システム)と呼ばれるeラーニングを組織的に運営するためのシステムを活用します。
LMSを活用することで、より大規模に効率的に学習履歴や成績データをeラーニングの改善や人事評価等に活かすことが可能です。
運営側のメリット(4)教材の更新や転用が簡単
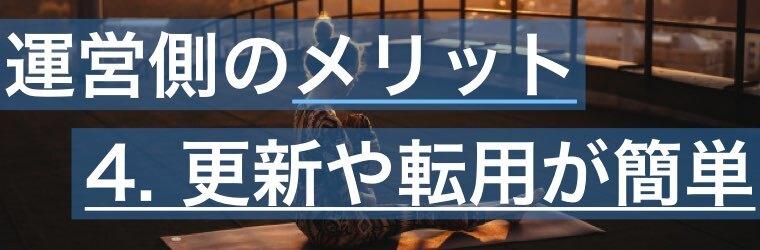
運営側の4つめのメリットとして、教材の更新や転用が簡単であることが挙げられます。
eラーニングには、運営側が簡単に教材を作成できるものもあります。
例えば、eラーニングを活用してコンプライアンス研修を実施する企業が増えていますが、法律の改正に合わせて微修正を行ったり、受講者の理解を深めるために最新の事例に差し替えたいという場合があります。
上記のような修正や追記があった場合でも、eラーニングの管理画面から部分的に新しい教材に差し替えることができます。
また、J-SOXの研修の一部にコンプライアンスで作った教材を差し込みたいというように、教材の一部を他の教材に転用することも簡単に行うことができます。
運営側のメリット(5)受講者ごとのプログラム構築がしやすい

運営側の5つめのメリットとして、受講者ごとのプログラム構築がしやすいことが挙げられます。
eラーニングの場合、教材の組み合わせを受講者ごとにカスタマイズして提供しやすいことも大きな特徴です。
中途入社や部署の異動などで、対象の社員が受講を終えていない講座がある場合、次回の研修時にそれらの講座を受けさせるといったことが可能です。
人材の流動化が一層進む中、受講者の状況に応じたプログラムの構築を柔軟に対応できることは大きなメリットです。
eラーニング受講側のメリット
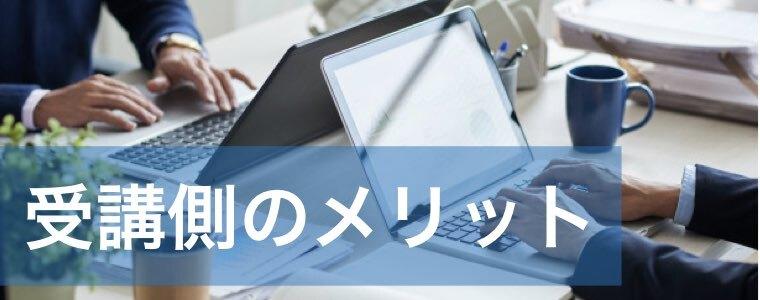
次に、eラーニングを受講する側のメリットをご紹介してきます。受講側のメリットは以下の5つがあります。
受講者側のメリット
- いつでもどこでも学習ができる
- 自分の理解度に応じて学習が進められる
- テストの結果がその場で分かる
- 視覚的にわかりやすい
- 何度でも受講できる
1つずつ詳しく見ていきましょう。
受講側のメリット(1)いつでもどこでも学習ができる
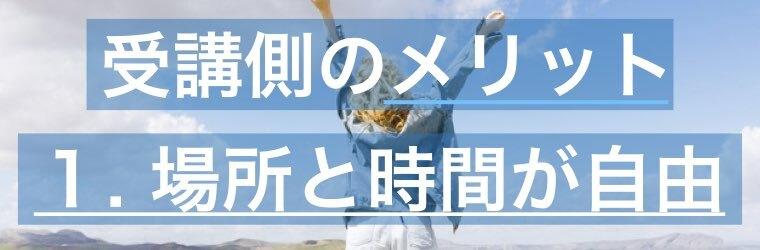
eラーニング受講側の1つめのメリットとして、いつでもどこでも学習ができるということが挙げられます。
最近のeラーニングはパソコンだけではなく、スマートフォンでも受講できるようになっており、通信環境さえあればどこでも受講できます。
集合研修のように同じ場所に同じ時間に集まる必要がないため、受講期間中、受講者の都合の良いタイミングで学習することが可能です。
受講側のメリット(2)自分の理解度に応じて学習が進められる
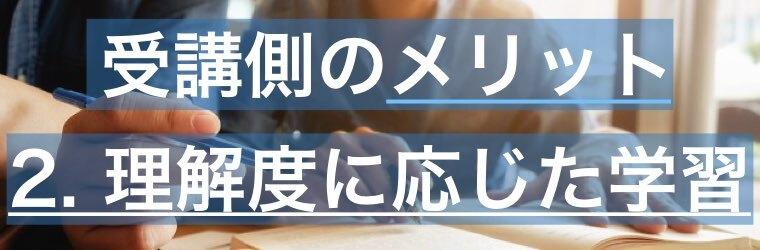
eラーニング受講側の2つめのメリットとして、自分の理解度に応じて学習が進められることが挙げられます。
人によっては、受講内容についてすでに知っていたり、逆に経験がなかったり、苦手な分野だったりと受講前の条件がバラバラです。また、一度では理解できないということもあるかもしれません。
eラーニングであれば、受講者の状況に応じて何度も同じ教材を学習したり、テストを先に受けたり、自分の理解度に応じて学習を進めることが可能です。
受講側のメリット(3)テストの結果がその場で分かる
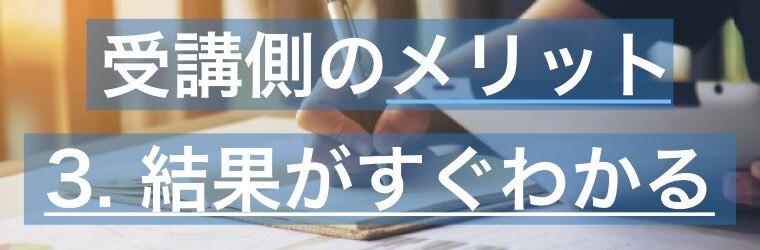
eラーニング受講側の3つめのメリットとして、テストの結果がその場で分かることが挙げられます。
eラーニングの場合、教材の中のテストの結果がその場でわかるため、学習の理解度がすぐにわかります。
結果がすぐにわかることで、再学習が必要な内容は再学習を、理解ができている内容は次の内容へと、学習を効率的に進めることができます。
受講側のメリット(4)視覚的にわかりやすい
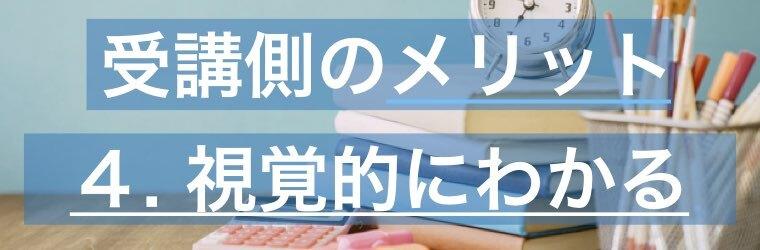
eラーニング受講側の4つめのメリットとして、視覚的にわかりやすいことが挙げられます。
パソコンやスマートフォンの画面を活かして、スライドだけではなく動画でも学習できます。また、クリックやタップといった受講者のアクションに応じて教材を展開させることも可能です。
集合研修でよく使われるテキストのような印刷物は、動画のように動きをつけることができません。
画面を通じて研修を行うからこそ、視覚的に理解を進められることがeラーニングのメリットと言えます。
受講側のメリット(5)何度でも受講できる
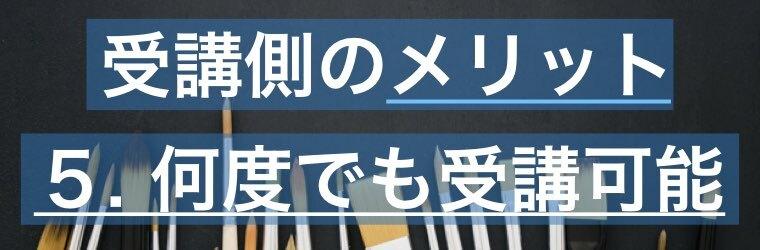
eラーニング受講側の5つめのメリットとして、何度でも受講できることが挙げられます。
同じ教材を受講しても、受講に対する理解度は人それぞれ違います。
リアルな講座として集合研修を実施する場合、基本的に再受講ができません。しかし、eラーニングであれば再受講が可能ですし、必要な部分だけを選んで受講し直すことも可能です。
受講者に意欲があれば、学習をしっかりと定着させることができるのがeラーニングだと言えます。
ここまで、eラーニングのメリットを運営側と受講側に分けてご紹介しました。それでは次に、eラーニングのデメリットをご紹介します。
eラーニングのデメリット

eラーニングのデメリットを運営側と受講側に分けてご紹介します。
| 運営側のデメリット | 受講側のデメリット |
|---|---|
|
|
それでは、運営側のデメリットをみていきましょう。
eラーニング運営側のデメリット
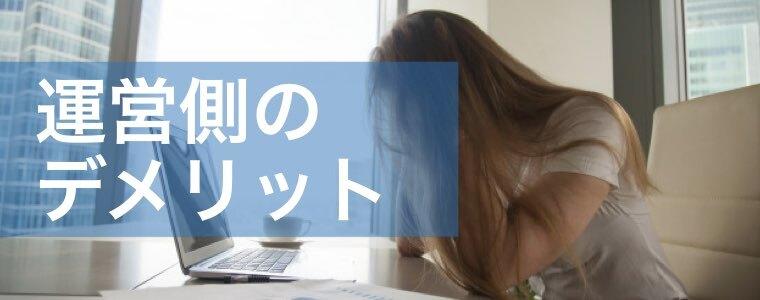
まずは、eラーニングの運営側のデメリットからご紹介をしていきます。運営側のデメリットとして以下の3つが挙げられます。
運営側のデメリット
- 一定のITリテラシーが必要
- 教材コンテンツの作成に時間がかかる
- 集合研修より強制力が弱い
それぞれのデメリットの詳細を確認していきましょう。
運営側のeラーニングのデメリット(1)一定のITリテラシーが必要
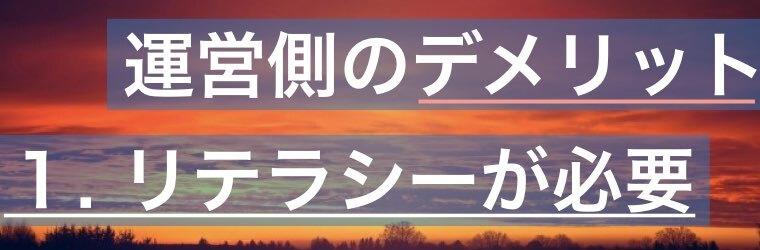
1つめの運営側のデメリットは、一定のITリテラシーが必要ということです。
eラーニングを受講するためには、パソコンやスマートフォンを操作し、自分の受けるべき講座を選んで受ける必要があります。
人によっては、eラーニングを受講するための操作自体がうまくできないという場合もあり、eラーニングの操作に関する問い合わせが運営者に来る可能性があります。
とはいえ、スマートフォンはほぼ全ての人が利用するツールとなっていますし、企業に勤めている方であれば、一定のリテラシーがある方がほとんどです。
また、直感的に利用できるように工夫をしているeラーニングもありますので、自社の社員のITリテラシーに不安がある企業は、使いやすさに注力している業者を選ぶのがよいでしょう。
運営側のeラーニングのデメリット(2)教材コンテンツの作成に時間がかかる
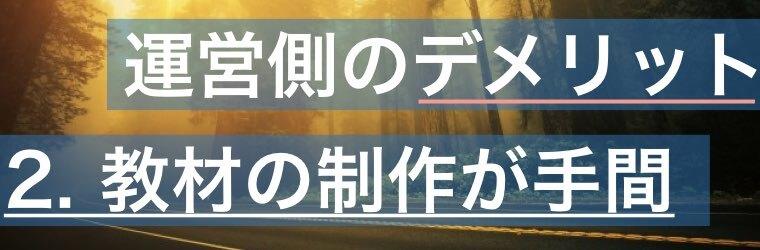
2つめの運用側のデメリットは、教材の作成に時間がかかるという点です。
eラーニングは、コンテンツをeラーニング会社から購入して受講させる場合と、学習プラットフォームとしてeラーニングを活用してコンテンツは自社で作成したものを受講する場合、の2パターンに分かれます。
後者のようにコンテンツを自社で作る場合、コンテンツの作成には相応の時間がかかります。
ただし、eラーニングによってはすでにパワーポイントでできている資料をそのまま教材として活用できたり、直感的に質問と分岐後のプログラムを作れるようになっていたりするものもあります。
自社で作成した教材コンテンツを活用したいと考えている場合は、コンテンツの作りやすさという観点で、eラーニング業者をチェックしてみてください。
運営側のeラーニングのデメリット(3)集合研修より強制力が弱い
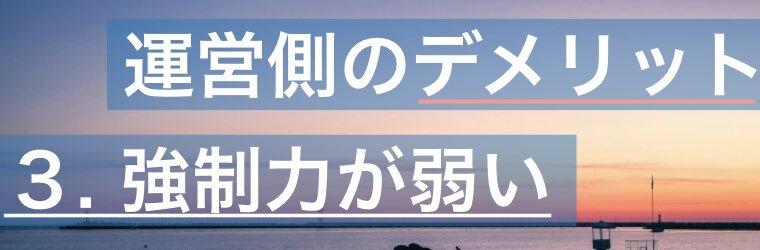
eラーニングの場合、受講者に受講がいつでもできる場を提供することができる一方で、それ以降の受講に対しては受講者本人の主体性が求められます。
一般的な集合研修の場合、実際に期日と受講場所、受講者を指定します。そのような集合研修の場合は、会社の指示として本人のモチベーションとは関係なく、指定の場所に行くことになります。
リアルな研修だからこそ強制的に研修を受けさせることができるという面もあり、eラーニングの場合は、受講に対する自由度が高いので本人の主体性も必要になってきます。
ただし、最近はeラーニング上で受講者同士の双方向性のあるコミュニケーションができるソーシャル機能など、オンライン上でもモチベーションや強制力を効かせる仕組みもあります。
最後に受講者側のデメリットについてまとめてみたいと思います。
eラーニング受講側のデメリット

eラーニングの受講者側のデメリットは以下の3つです。
受講者側のデメリット
- 実技の必要な科目の学習に向かない
- インターネット環境が必要
- 講師や他の生徒との人的ネットワークが作りにくい
それでは、詳細をみてみましょう。
受講側のeラーニングのデメリット(1)実技の必要な科目の学習に向かない
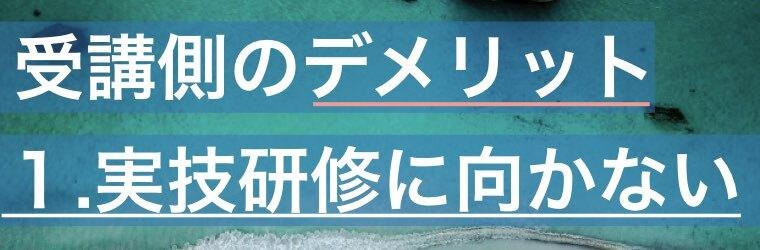
受講側のeラーニングのデメリットとして1つめは、実技の必要な科目の学習に向かないということです。
パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイス上での座学としては学習できるものの、実技の技術を学ぶという点では実際に手を動かした方が学習効果が高くなります。
例えば、料理を覚えるために、eラーニングで作り方を学ぶごとはできます。しかし、実際に調理過程を行うことで、焼いた時の食材の色の変化や同時並行でしておくべき作業など、座学で学ぶ以上の情報を得ることができます。
ただし、プログラミングやパソコンのソフトウェアの研修など、パソコン上で実践する実技については、eラーニングでパソコン上で学ぶことで実技のトレーニングとしても十分な学習効果を得られます。
受講側のeラーニングのデメリット(2)インターネット環境が必要
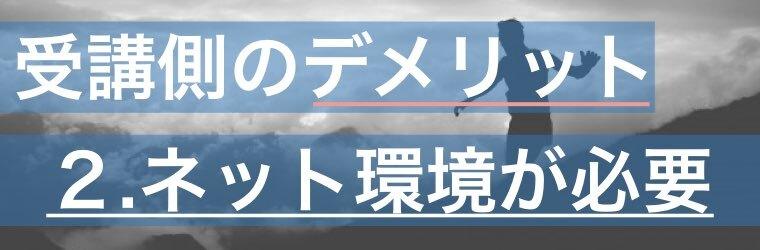
受講側のeラーニングのデメリットとして2つめは、インターネット環境が必要だということです。
いつでもどこでも受講できることが大きなメリットであるものの、インターネットが通じにくい環境に行ってしまうと、受講そのものが進められなくなります。
ただし、音声やスライドを事前にダウンロードして受講できるeラーニングもありますので、通信環境が悪い状況での受講が予測される場合は、オフラインでの受講対応ができるeラーニングを選ぶとよいでしょう。
受講側のeラーニングのデメリット(3)講師や他の生徒との人的ネットワークが作りにくい
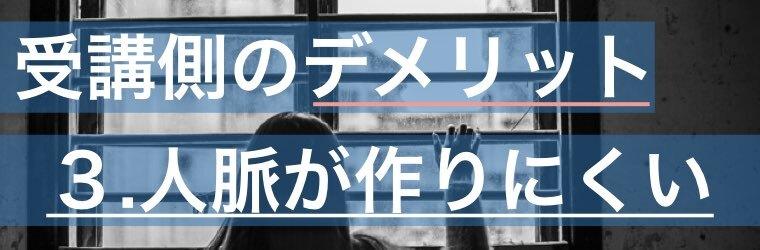
3つ目の受講側のデメリットは、講師や他の生徒との人的ネットワークが作りにくいことです。
オンラインでの受講の場合、受講期間はあるものの、その中での受講開始のタイミングは受講者ごとにバラバラです。
そのため集合研修にあるような、同時に一緒に同じ内容を受講するというシーンは基本的にはありません。その結果、受講中に受講者同士のネットワーキングをしたり、講師と対面で話すことで相互理解を深めるといったことがありません。
ただし、オンライン上でもソーシャル機能によって受講者同士が学習状況を共有したり、同じ課題を一緒に相談しながら解決するというeラーニングもあります。
また、講義をオンライン上で生放送で行うことで、集合研修のように同じ研修を同時に受講することも可能です。
まとめ

本記事では、eラーニングのメリットとデメリットを運営側・受講側に分けてご紹介しました。
| 運営側 | 受講側 | |
|---|---|---|
| eラーニングのメリット |
|
|
| eラーニングのデメリット |
|
|
eラーニングは運用コスト削減をしつつ、学習効果を高めることができるツールとして企業内研修で活用することが定着してきました。
今回ご紹介したとおり、デメリットもあるため、自社の導入目的に合わせ、補完できるeラーニングを選んでみてはいかがでしょうか。