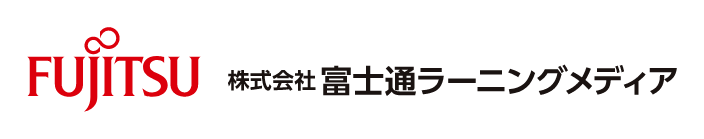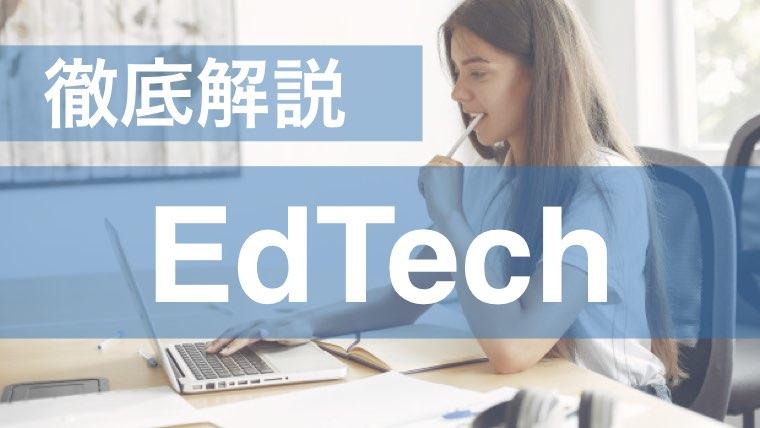- トップ
- 「ブログ」LMSラボ
- ICT教育とは〜市場・背景や国・教育現場の動向・海外先進国事例〜
- eラーニング
- 研修
ICT教育とは〜市場・背景や国・教育現場の動向・海外先進国事例〜

近年、多くの教育現場でICT教育の導入が進んでいます。ICT教育とは、情報通信の技術を生かした教育のことです。
インターネットが世の中に浸透し、私たちの生活に欠かせなくなっていることからも、各教育機関にICTが導入されることは自然な流れといえます。
最近では、新型コロナウイルスによる休校などの対策としてオンライン授業などが導入されていますが、これもICT教育の1つです。
では、パソコンやデジタル機器を利用すればICT教育か、というとそうではありません。
- ICT教育という言葉は聞いたことがあるが、よく理解できていない
- ICT教育を実践するには、どのようにしたらよいか
- 教育現場ではどのようにICT教育を実践しているのか知りたい
本記事では、ICT教育とは具体的にどういうものなのか、ICT教育のメリットや問題点、活用事例などを説明します。
目次
ICT教育とは
ICT教育とは、情報通信の技術を生かした教育のことです。
ICT教育についてより理解を深めるために、ICT教育の定義と市場規模、ICT教育が推進される背景、ICT教育が抱えている課題について解説します。
ICT教育の定義
ICTとは、Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のことです。
ICT教育は、学校教育でパソコンやデジタル機器を活用することを指します。
ICT教育の一例
- プロジェクターを利用する
- 電子掲示板を活用する
- 授業中に生徒がパソコンで板書を取る
- 授業のプレゼンにタブレットを使用する
ICTは、企業でも活用されており、学校の授業で取り入れていくことも難しくありません。
昨今、インターネットの急速な発展に伴い、ICTが教育現場にも浸透してきています。
教員も生徒もスマホやパソコンを日常的に利用しているため、活用に抵抗はないツールといえますが、学習効果を高めるためにどのように扱うべきか考える必要があります。
では、日本におけるICT教育の浸透状況をみていきます。
ICT教育の市場規模
学校のICT環境整備の状況について、2018年3月1日時点での文部科学省が発表したデータがあります。
<学校のICT環境整備の現状>
- 教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数 5.6人/台
- 普通教室の無線LAN整備率 34.5%
- 超高速インターネット接続率( 30Mbps以上) 91.8%
- 普通教室の電子黒板整備率 26.8%
参照元:総務省 教育情報化の推進 (6)教育の情報化の現状と今後の方向性(PDF)
以上のように、デジタル端末や無線LANの配備などインフラ面の整備を進めている途中段階だと言えます。
ICT教育が推進される背景
国全体でICT推進していくという政府の方針の下、文部科学省を中心にICT教育が推進されています。
第二次安倍内閣が掲げた成長戦略のひとつ「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」では世界最高水準のIT社会の実現、を掲げています。
なぜ、国はICT教育を早急に推進するのでしょうか。
理由は2つあります。
1.今の社会に求められるスキルへの対応
ICT教育が普及する前の学校授業は、黒板に書かれた板書をノートに写し、暗記してテストに臨む、というスタイルでした。
しかし、インターネットが普及した現代は、膨大な知識や暗記力はそれほど求められなくなっています。分からないことは、インターネットですぐに調べられるからです。
これからの時代に求められるのは適切な情報を選び、活用していくスキルです。そのためにICTを学校教育に導入することが必要になるのです。
2.わかりやすい授業を実現する
文字だけでなく、映像や音を使用して五感に訴えかけた授業の方が印象に残り、記憶に定着しやすい、と言われています。
授業がつまらないと感じていた生徒が、ICTを取り入れることで学習に興味を持つ可能性もあり、生徒が意欲を持って学習する、という面でもICT教育は期待されています。
ICT教育の課題
国としてICT教育を推進している最中ですが、まだまだ課題もあります。
まず、インフラの整備が十分に整っていないことが挙げられます。
ICT教育には無線LANの設置が必要ですが、地域格差があります。
無線LANの整備状況は、2019年3月時点で、全国1位が静岡県の73.6%、最下位が新潟県の13.3%となっています。
参照元:文部科学省 平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
パソコンも2010年度中には1人1台使用できることが目標になっていましたが、2017年3月の時点で、1台を平均5.9人で使用している状況です。
格差は地域だけではありません。ICT教育の必要性は理解しているものの、関係者の認識には差があるようです。
特にICT教育に対する学校や教育委員会、行政の姿勢の差も浮き彫りになっています。
ITリテラシーが高い教員ばかりではありません。教員が端末やアプリを使いこなせていない、という問題もあり、解決が急がれます。
ICT教育は、単にデジタル端末を利用するだけでは不十分です。活用するための十分な指導力とフォローがないと、ICT教育を推進することはできません。
国が推進するICT教育

ICT教育の推進は政府の方針であり、文部科学省を中心に進められています。
2019年に行われた教育関係者向けセミナー&展示会「NEW EDUCATION EXPO 2019(NEE2019)」では、文部科学省と総務省、経済産業省の各省がICT教育を推進するための施策を発表しました。
文部科学省、経済産業省、総務省のそれぞれがどのようにICT教育を推進しようとしているのかをみていきます。
文部科学省はSociety5.0時代に向けてICT教育を推進
文部科学省は、2019年6月に「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」という報告書を発表しました。
その中でSociety 5.0 時代を見据えて、義務教育9年間を見通した児童生徒の発達段階に応じた学級担任制と教科担任制の在り方、習熟度別指導の在り方など今後の指導体制についてまとめられています。
Society 5.0 とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題を解決する人間社会のことです。
Society 1.0が狩猟社会、 Society 2.0が農耕社会、 Society 3.0が工業社会、 Society 4.0が情報社会を指しています。Society 5.0 は我々人間が目指すべき未来社会のあるべき姿として提唱されています。
経済産業省はEdTechの切り口からICT教育を推進
経済産業省は「未来の教室とEdTech研究会」を設置し、ICT教育を推進しています。
2019年6月に発表された第二次提言では、以下のようにまとめています。
- 学びのSTEAM化
- 学びの自立化・個別最適化
- 新しい学習基盤づくり
それぞれを解説していきます。
1.学びのSTEAM化
一人ひとり違うワクワクを核に、「知る」と「創る」が循環する、文理融合の学びに。
子供達が未来に向けた社会課題に触れてワクワクする感覚を呼び覚ますとともに、専門的な知識を効率よく習得する(知る)ことと、課題発見と解決の試行錯誤を繰り返す「創る」ことが循環して学べる教育基盤をつくることを目指しています。
2.学びの自立化・個別最適化
一人ひとり違う認知特性や学習達成度等をもとに、学び方を選べる学びに。
一人ひとりが異なる個性を持っていることを前提にデジタルに記録された「学習ログ」をもとに、のびのびと才能を伸ばす多様な選択肢のある学習環境をつくることを目指しています。
3.新しい学習基盤づくり
学習者中心、デジタルファースト、社会とシームレスな学校へ。
1人1台パソコンを使用するなど、ICT環境の整備や部活動に縛られない放課後の過ごし方を充実させること、そして特別免許状制度などを設けて教員が学校外の人材に触れて専門性を身につけられる環境をつくることを目指しています。
参考:未来の教室(経済産業省)
総務省は教育ICTで4事業を推進
総務省はハードとソフトの2つの側面から以下の4つの事業を展開しています。
<ハード>
- 先導的教育システム実証事業
「教育クラウド・プラットフォーム」を標準化。これにより、いつでもどこでも低価格の端末でも、自分に合ったデジタル教材が利用可能になり、地域や経済的事情による教育格差の解消を図っています。 - スマートスクール・プラットフォーム実証事業
文部科学省と蓮階して教職員が使用する「校務系システム」と生徒が利用する「授業・学習系システム」間での安全かつ効果的、効率的な情報連携を標準化しています。
<ソフト>
- 若年層に対するプログラミング教育の普及促進
論理的思考能力の課題解決力を育てるために、プログラマー、システムエンジニアに必須となるプログラミング教育を義務教育に取り入れることを平成28年度より普及推進しています。 - 地域ICTクラブ普及推進事業
ICT教育の一環として、学校だけでなく放課後や休日に課外活動を推進しています。他の世代との交流や地域の企業の後任育成などにも効果が期待されています。
参考:教育情報化の推進(総務省)
ここまで、行政の動きについて解説をしてきました。なお、各省の取り組みについては以下の記事でも詳しく解説をしてます。
次に、教育現場である学校でのICT教育の状況について見ていきましょう。
学校で活用されるICT教育

学校で活用されているICT教育には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここからは幼稚園、小学校、中学校、高校のそれぞれで取り入れられているICT教育について紹介していきます。
幼稚園のICT教育
近年では、幼稚園でもICT教育が推進されています。
長野県で20か所以上の保育園と幼稚園を経営する進学会では、2012年よりICTを教育に導入しました。
先生自身がITリテラシーを向上させる必要があるため、ICTを利用して園児の状況を一元管理することから始めました。
それまで、園児の出欠情報は担任のみが把握していましたが、ICT活用により伝達ミスが解消しました。
幼稚園バスのロケーションシステムも導入しました。
送迎バスの位置情報がスマホで閲覧できるため保護者からの電話連絡が減り、先生の作業工数が軽減しました。
2012年からは年長児を対象にタブレット教育が行われています。1人1台タブレットが渡されて学習を行うため、園児それぞれのペースで学習ができます。
アニメーションや音声が園児を刺激し、学習に興味を持ってくれるのもタブレット学習のメリットと言えます。
小学校のICT教育
小学校では、生徒がイメージしやすいように、動画やアニメーションなどの視覚的な説明でICTを活用しています。
例えば算数の図形の問題や漢字の書き方などを動画で見せることで、イメージしやすく記憶に定着しやすいといった効果が期待できます。
また、小学校では2020年からプログラミング教育が義務化されます。「プログラミング」という科目が設置されるわけではなく、理科などの時間の中で実施されるようです。
プログラミングの技術的な技能を身につけるというよりも、プログラミングを通じて論理的な思考力を身につけるということが狙いになっています。
中学校のICT教育
中学校では小学校よりも高度な概念を扱うため、言語でイメージしにくいものを扱う時にICTを活用しています。
例えば、天体の動きをシミュレーションしたり、歴史の授業でWeb教材を利用したりなどです。
生徒に1台ずつタブレットが支給されていれば、各生徒が自分自身でシミュレーションし、実感することもできます。
タブレットが配布されている中学校も増え、授業が始まるとともに先生も生徒もタブレットを出す、というシーンも珍しくありません。
生徒がタブレットで、課題を提出したり、テストを実施したりなど、活用方法は多岐に渡ります。
先生は、テストが紙のときに行っていた集計作業や物理的に管理する手間がなくなり、効率的に業務を進められます。
高校のICT教育
高校になると学ぶ知識量も豊富になります。
そのため、クラスでフラッシュカードを使用して英単語を確認することや、発表時にパワーポイントを利用するなど、企業でICTを利用している状況により近い方法で活用されています。
また、生徒には大学受験のための学習アプリ、動画学習コンテンツなども定着しています。
高校生にとっては、ICT環境なしに学習を進める方が難しい環境になりつつあるといえるでしょう。
ICT教育の海外先進国の事例
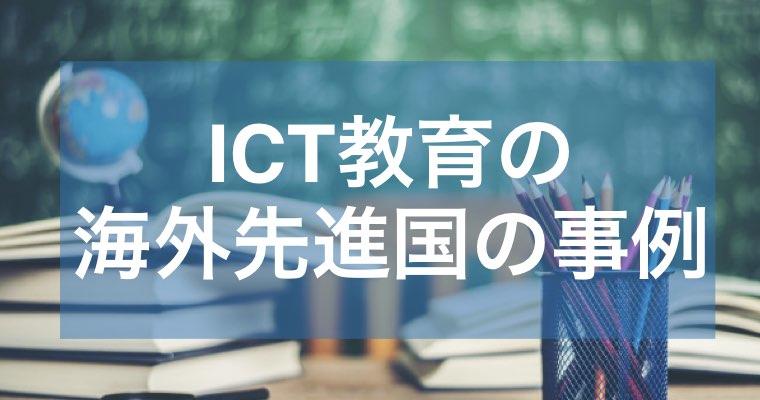
ここまで、国内の各学校におけるICT教育の状況について見てきました。
それでは、海外のICT教育事例をみていきましょう。
アメリカ
IT大国であるアメリカでは、教育においてのICT化が進んでいます。
2015年のオバマ政権において「Computer Science For All」という政策のもと、コンピューターサイエンスが小学校・中学校・高校の12年間、必須科目に指定されたことで、ICT教育が加速しました。
アメリカでは、生徒がICTを活用しやすい環境を整備しているだけでなく、教員がICTスキルを習得するための取り組みにも力を入れています。
授業中でも必要に応じて生徒にスマホやタブレットの使用を許可するなど、デジタル機器の使用に寛容です。
学校内では担当者がICTの活用事例を学校のHP上やメールで共有し、ICTの活性化を推進しています。
韓国
韓国でも、ICT教育に力をいれており、計画的に整備を進めてきました。
まず、2006-2009年に、20校を対象に、電子黒板、無線LAN、モバイルパソコンを整備しました。
2007-2013年には、100校を対象にタブレット型のデジタル教科書を導入しています。
その他にも教育行政情報システム NEIS(NEIS :National Education Information System))の導入など積極的にICT教育の推進が行われています。
オランダ
オランダもICT教育に力を入れている国の1つです。
オランダでは、非常勤ですが多くの学校にICT教員という担当者がいて、積極的にICTの教育を推進しています。
オランダ教育文化科学省のICT活用推進機関が初等中等教育向けにデジタル教材のプラットフォームを提供するなど、国からの積極的なICTの活用支援があります。
また、支援が必要な児童のためにタッチスクリーンボードを導入するなど、学校の状況に応じて柔軟にICT化を進めているのもオランダのICT教育の特徴です。
シンガポール
シンガポールはICT教育の先進国です。
シンガポールには自然資源がほどんとないこともあり、人材の育成が国家の重要施策として考えられています。ICT教育の分野においては、2008年からFuture School @ Singapole という政策を進めました。
国主導で教育機関にICT化を進める政策で、国が指定した学校では1人1台のパソコンが利用できる環境が整備されています。
また、ICT教育に対する教員の意識も高く、教員がITを活用するためのノウハウも体系化されています。
他国に比べて素早くICT教育を取り入れた国であり、例えば、小学生がマイクロソフトのパワーポイントでプレゼンテーションする、といった光景は当たり前のものになっています。
フィンランド
フィンランドは、90年代からICT教育に取り組んでいます。
その結果、インターネットの整備率は基礎学習、高校ともに100%で、ICT教育が圧倒的に進んでいます。
また、どの学校にも電子黒板があり、生徒1名に対して1台のタブレット、またはPCが用意されています。
同国は、ハードウェアの整備だけではなく、各生徒の進度にあわせて学習を進めることができるようになっているなど、ソフト面でも進んでいます。
さらに、VR技術を学習に生かす試みがされるなど、ICT教育の先進国として新しい取り組みを行っています。
まとめ

本記事では、ICT教育について解説しました。
ICT教育は推進されていますが、地域格差や意識の違いなど、まだまだ解決しなければならない課題があります。
デジタル機器の導入などのハード面ではなく、教える立場の人もICTを使いこなせるスキルが求められるため、教育者の人材育成も重要です。
日本が世界的に競争力のある人材を育てるにはICT教育は不可欠です。
行政や教育現場においてICT教育をどのように活かしていくのかが、問われています。