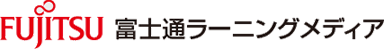- 人材育成
- 組織開発

「パフォーマンスマネジメント」は、人事担当者でも初めて聞くという方が多い言葉かもしれません。これは、従業員一人一人のパフォーマンスを向上するために、モチベーションを上げること、その成果として組織の目標を達成していくという取り組みを示すマネジメント手法です。その考え方と、導入の意義を解説します。
パフォーマンスマネジメントとは?
パフォーマンスマネジメントとは、従業員のパフォーマンスを高めるために、人事部や管理職が従業員と一緒に目標を考え、従業員の行動を見守り、出てきた結果を次の目標設定にフィードバックすることです。
従来の人材管理と何が異なり、どのような長所があるのか見ていきましょう。
パフォーマンスマネジメントの考え方
パフォーマンスマネジメントは、マネージャーとメンバーが連動しつつも、メンバー一人ひとりが事業主であるかのように自主的に考え行動し、個人の成長を促していく、という考え方を採用しています。
人事部や管理職は、従業員の能力や仕事ぶりを評価するという従来の立場から、コーチングなどによって従業員をサポートし、結果を出させる役割へと変化することが求められます。一方の従業員は、目標達成するために必要なプロセスを理解し、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら成長する姿勢が求められます。
目標管理制度(MBO)との違い
会社側が従業員の目標や行動に積極的に関与する手法として「目標管理制度(MBO、Management by Objectives)」が用いられることが多いですが、パフォーマンスマネジメントはMBOとは異なります。
MBOは1年ごとに「目標、結果、評価」を繰り返す手法です。通常、年度当初に管理職と従業員が面談し、目標数値を設定します。従業員は行動計画を立てて行動し、管理職は従業員が行動計画通りに行動できているか、また、年度終盤に目標を達成できたかを評価します。
パフォーマンスマネジメントでも、管理職と従業員が面談し、「目標、結果、評価」を行います。ただパフォーマンスマネジメントでは、従業員のモチベーションを上げることと、結果に至るまでのプロセスに注目します。
またパフォーマンスマネジメントでは、面談は1年1回に限定せず、従業員が一定の結果を出したらすぐに評価してフィードバックすることもあります。
パフォーマンスマネジメントの導入について
パフォーマンスマネジメントについてイメージすることはできたでしょうか。それでは次に、企業がパフォーマンスマネジメントを導入するメリットや、実際の導入方法について解説していきます。
導入するメリット(意義)
パフォーマンスマネジメントを導入した企業には、スピード感が生まれます。
さきほど見た目標管理制度(MBO)は、実はかつては大きな成果を上げていました。ところが経済のグローバル化と情報伝達の高速化により、1年間ごとに目標設定と結果評価を行うMBOでは、世の中の動きについていけなくなることが増えてきたのです。
パフォーマンスマネジメントでは、従業員が結果を出したらすぐに管理職による評価が行われ従業員にフィードバックするので、スピード経営ができます。
従業員にとっても、行動や結果の記憶が鮮明なうちに管理職から評価してもらえるので、学習効果が高まるというメリットがあります。
また、1年ごとではなく、随時フィードバックするので柔軟に変化に対応でき、よりよい成果へとつながるというメリットもあります。
- 企業のメリット:スピード経営ができる。変化に柔軟に対応できる。
- 従業員のメリット:軌道修正がしやすくなりパフォーマンスを上げられる。
導入のポイント
パフォーマンスマネジメントを組織に根付かせるためには、管理職や人事部員がアクティブリスニング(傾聴)スキルなどのコーチングのスキルを身に付ける必要があります。
従業員の目標設定は、管理職と従業員本人が一緒に行います。このとき管理職は「やらせたいこと」を従業員に押し付けるのではなく、従業員のモチベーションや能力を高める方法を一緒に考えてください。
アクティブリスニングとは、聞き役に徹することで、相手の能力を引き出す手法です。管理職が従業員から有意義な話を引き出すためには、面談の前に従業員の能力やこれまでのパフォーマンスを把握しておく必要があります。その上で面談に臨み、うまく聞き出すようにしてください。従業員本人が話し出すのを待つ姿勢も大事なポイントとなります。
また聞くだけでなく、実際のパフォーマンスを評価し、次につなげるコーチングのスキルも重要となります。どの点がよく、どこを改善すると次に繋がるのか、などをわかりやすく説明できると、従業員が気付いてなかったポイントに目がいき、気づきがうまれるようになります。
パフォーマンスマネジメントを導入した企業はどうなる?

従来型の人事管理では、評価に重きが置かれ、従業員の中に序列が生じてきました。評価をしてくれた上司と評価を受けた従業員の縦のつながりは強くなりますが、従業員の中で優劣の序列を付けざるを得ないため、横のつながりに支障が生まれることがありました。
しかし、パフォーマンスマネジメントでは「誰かよりも良い(または低い)」とは評価せず、「個人特性」に注目しますので、上下関係ができにくくなります。
そのため従業員同士のコラボレーションが生まれやすくなり、横のつながりが強くなるのです。
だからといって、パフォーマンスマネジメントによって縦のつながりが弱くなるというわけではありません。
管理職は、自分のスタッフたちのパフォーマンスを常に観察し、頻繁にフィードバックするようになるので、コーチング・スキルが身に付きます。このことによって管理職はスタッフからより信頼されるようになり、チーム活動が円滑に進むようになるのです。
まとめ
いかがでしたか?この記事ではパフォーマンスマネジメントとは何か?について基本的な内容を説明させていただきました。パフォーマンスマネジメントは、上手に導入すれば企業をよりよくしてくれるものなのではないでしょうか。
様々な詳しい解説本も出版されており、人事部スタッフや管理職向けのパフォーマンスマネジメント研修を行う企業もあります。パフォーマンスマネジメントの導入を円滑に進めるためにも、是非人事担当の方は本や研修などで先進事例を学んでみてくださいね。