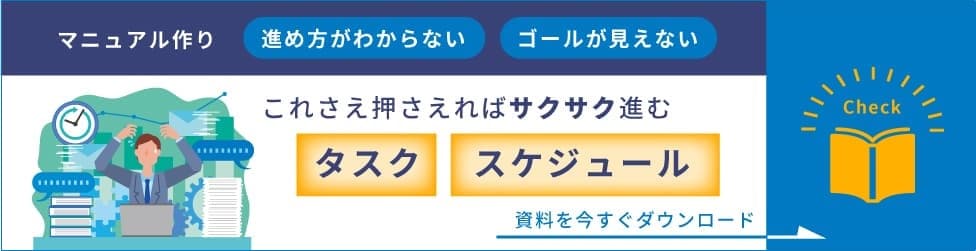生産性向上とは?業務効率化との違いやメリット・実現のための6つのステップを解説
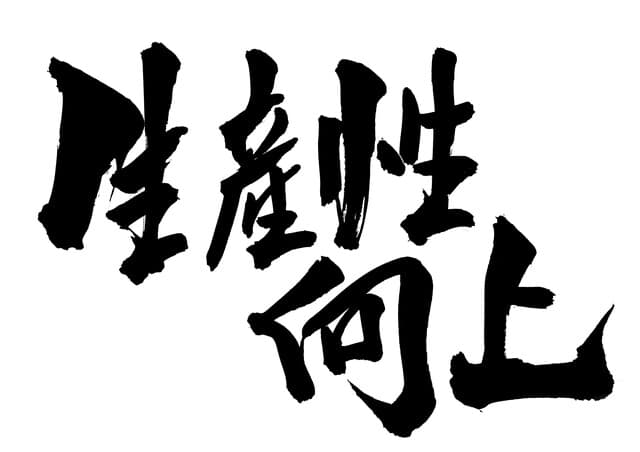
生産性とは、主に企業活動においてよく聞く言葉ですが、投入資源から生み出された生産物の割合を表す指標です。少ない資源で多い生産物を生み出した場合、生産性が高いということになります。
商品やサービスを生産する企業活動において、生産性は重要な課題ですから、生産性の向上を常に意識していく必要があります。また、「これを開発するのに1年かかった…」というように従業員も現場で実感することがありますので、経営者やマネージャーだけでなく、企業にいるメンバー全員が意識する課題といえます。
この記事では、生産性の向上とは何か、業務効率化との違いは何か、生産性向上のメリットや必要性について、わかりやすく解説します。さらに、生産性向上のために必要な6つのステップについてご説明しますので、どんな施策が生産性向上につながるのか、イメージを持っていただければ幸いです。
生産性向上とは?概要・業務効率化との違い・必要性を解説
まず初めに、生産性の向上の概要や、よく耳にする「業務効率化」との違い、生産性向上が企業活動において求められる理由は何かについてご説明します。
概要
生産性とは、計算式で表すと、以下のようになります。
生産性=生産物(output)/投入資源(input)
つまり、生産性が高い状態とは、次の2つの状態を指します。
- 何かを生産するために投入した資源が、少なければ少ないほど生産性が高い
- 投入した資源で生産した生産物が、多ければ多いほど生産性が高い
例えば、新たな保険商品を開発していたところ、既存の仕組みを活用して顧客の要望に沿う商品ができたならば、開発にかかる人手などの資源が少なくて済み、生産性が高い状態といえます。
さらに、生産性算出には以下のようなバリエーションがあります。
1、物的労働生産性
- 労働生産性(1人当たり)=生産量/労働者数
- 労働生産性(1時間当たり)=生産量/労働者数×労働時間
- 資本生産性=生産量/資本ストック量
2、付加価値労働生産性
1の式の、分子を「付加価値額」にしたものです。付加価値額とは、財務上生み出される金額ベースの価値のことを指します。
- 労働生産性(1人当たり)=付加価値額/労働者数
- 労働生産性(1時間当たり)=付加価値額/労働者数×労働時間
- 資本生産性=付加価値額/資本ストック量
3、全要素生産性(TFP)
全要素生産性(Total Factor Productivity)は、労働力や資本だけでなく技術の進歩といった、あらゆる資源を計算に加入して求める算出方法です。
- 生産量/(労働+資本+原材料など)合成投入量
- 付加価値額/(労働+資本+原材料など)合成投入量
業務効率化との違い
生産性向上と、業務効率化の違いについてご説明します。
業務効率化とは、現状は非効率的な状況にある業務について、ムリ・ムダ・ムラのある工程を排除し、改善して効率的にしていくことを指します。生産性向上とは、より多く生産物を生み出し、より少ない資源を投入する動きですので、投入資源を削減する業務効率化は、生産性向上のための施策の1つといえます。
ただし、「業務効率化によって少ない資源を投入することになったが、生産物も少なくなった」という状況もあり得ますので、両者を区別し、目的に応じた適切な施策を行うことが大切です。生産性向上を目的とするならば、生産物と投入資源のバランスをみながら施策を行います。業務効率化を目的とするならば、投入資源を最小化できる策を行うことになります。
生産性向上が求められる理由

生産性向上は、企業活動を行う上での必須課題ですが、社会的に生産性向上が求められる理由が2つあります。
1つは、少子高齢化による人口減少です。日本の人口は2006年に1億2,774万人でピークに達したあとは、減少の段階に入っています。労働力人口(15歳~64歳)という観点でも、2011年から2021年の10年間で、横ばいから少しずつの減少傾向にあります。
2つ目としては、日本企業の国際的な労働競争力の低下です。
IMD(国際経営開発研究所)によれば、64の国と地域の中で、日本は総合的な順位が31位と低迷しています。特に生産性・効率性などの項目であるビジネス効率性は、2014年以降ずっと下がり続けています。
出典:International Institute for Management Development「世界競争力年鑑」2021年:この競争力は、経済状況、政府効率性、ビジネス効率性、インフラの4つの大項目で審査されるもの。2021年の日本の経済状況は12位、政府効率性は41位、ビジネス効率性は48位、インフラは22位。
また、公益財団法人日本生産性本部のレポートによると、2020年の日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟38カ国の中で23位、一人当たり労働生産性は28位と低位にいます。
こうした状況を踏まえ、労働力人口の確保や国際的競争力の強化に加えて、労働生産性の向上や長時間労働の是正などをねらいとして、働き方改革に係る法律が2019年から施行されました。いわば、生産性向上は国を挙げて全力で取り組むべき課題となっているのです。
生産性向上が企業に与える3つのメリット
生産性の向上が、企業に与えるメリットは3つあります。
- 従業員満足度の向上
- 顧客満足度の向上
- コスト削減
どのようなメリットなのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
【メリット1】従業員満足度の向上
1つ目のメリットが、従業員満足度の向上です。
生産性向上のために、さまざまな施策が行われます。例えば、業務のムダな部分を見直したり、自動化できる部分は機械やシステムによる自動化を行ったりすることで、注力すべきことに集中できる働きやすい環境になります。残業時間が減り、余裕のある人繰りで休暇が取りやすくなり、従業員のワークライフバランスが整います。
また、従業員のスキル習得をサポートすることで、課題解決が早まり生産性が上がり、従業員は自分の成長を感じることができます。
これらのことから、従業員は「もっとこの職場で頑張ろう」というモチベーションが高まり、満足度が向上します。
【メリット2】顧客満足度の向上

2つ目のメリットが、顧客満足度の向上です。
生産性向上の施策により、ムダな作業をやめることで余裕が生じ、かつ従業員のスキルが上がると、顧客への対応の質が変わってきます。例えば、営業や対応窓口など顧客に接する担当者は、より迅速に幅広いリクエストに応じたり、より役立つことを提案できたりします。
また、顧客には直接対応しない工場やバックオフィスの従業員も、業務を見直し、ムリやムラを排除し、職場の生産性を上げることで、良い製品をより低コストで生産でき、よりよいサービスを生み出せるようになります。
これらのことが、顧客満足度の向上につながります。
【メリット3】コスト削減
3つ目のメリットが、コスト削減です。
生産性向上は、少ない投入資源でこれまで以上の生産物を生み出すことですから、投入資源の量や質を見直すことになります。例えば、原材料の仕入れ方を変更する、同じ作業をまとめて行うなどの工夫をして少人数化する、テレワークを導入してオフィスの賃料や光熱費を削減する、などの施策を検討します。
単純に「人手を減らす」「コストを半分にする」といった強硬策ではなく、生産性向上につながるようなコスト削減を行うと、減らせたコストを新商品の開発や新システム導入、福利厚生など、さらなる事業発展や労働環境改善に充てることができ、従業員満足度や顧客満足度との良い循環が生まれます。
お役立ち資料:『『業務マニュアルをクラウド化するメリットとは?』~業務マニュアルクラウドツールをお悩みの方は必見!~』
生産性向上に必要な6つのステップ

生産性向上の施策を考える上で必要な、6つのステップをご紹介します。
あらゆる生産性向上策を講じていくためには、このように段階を追って行うと漏れなく洗い出すことができます。ぜひ参考にしてみてください。
【ステップ1】現状業務の見える化
1つ目のステップは、現状業務の「見える化」です。
生産性の算出に用いられる要素は、労働者数や労働時間、資本ストック量などです。これらの要素は、例えば次のようなものから成り立っています。
- 量的要素(労働者数、労働時間、原材料、有形固定資産、商品原価に組み込む光熱費などのコストなど)
- 質的要素(業務手順、作業ノウハウ、ビジネスモデル、スキーム、従業員の現在のスキルや実績、ポテンシャルなど)
これらを改善していくために、まずは現状を見える化して把握します。見える化のためには、次のような情報を用意しましょう。
- 業務のマニュアルや手順書
- フローチャート
- 組織図
- システム相関図
- スキルマップ
- 従業員労働時間
- 課題達成表や目標管理シート
- 原価管理表
【ステップ2】業務の取捨選択
2つ目のステップは、業務の取捨選択です。
ステップ1で洗い出した情報を分析し、注力すべき要素と現状維持の要素とに色分けします。例えば、主力商品に関わるコストや、これから展開していきたいビジネス、力を入れたい部門や部署などには赤色でマークします。現状維持をしていく業務、もしくは慣習や付き合いでやっていたがいずれやめたい業務については、青色でマークします。
このように色分けをして、赤色でマークしたものについては、コストの増加率以上に生産物を多くしていく施策を行います。青色でマークしたものについては、コスト削減の施策を行います。
【ステップ3】アウトソーシングの検討

ステップ1で要素を洗い出し、ステップ2で色分けをしました。ステップ3から6は、生産性向上のための具体的な施策をご紹介します。
まずは、アウトソーシングを検討します。アウトソーシングを検討するには、今どのようなアウトソーシングのサービスがあるのかを調査します。例えば、以下のようなサービスがあります。
営業事務
ドキュメント作成
ライティング・編集
人事・労務管理・採用・研修
経理・給与計算
総務
カスタマーサポート
データセンター
データ入力
マニュアル作成
デザイン・コーディング
IT運用
広告運用
プロジェクト運営
企業に必要な業務が数多くカバーされており、これらだけで会社が一つ作れてしまうほどのバリエーションがあります。さまざまな業者がサービスを提供していますので、比較して導入コストをじっくり検討しましょう。
導入の判断のポイントは、自社の従業員が業務を行う場合と比較して、費用が抑えられる場合や、自動化や機械化などにより業務の量や質が向上する場合は、導入していくとよいでしょう。
【ステップ4】人材の再配置
4つ目のステップは、人材の再配置です。
従業員が持っているスキルや強み、これまで業務上どのようなパフォーマンスをあげてきたかを鑑みて、適材適所の部署やポジションに再配置します。スキルとは、業務上求められる知識や資格、技術であり、強みとは、チームで働く上で発揮される、協調性やリーダーシップなどの個人の能力を指します。このほかに、潜在的な能力であるポテンシャルを加味することも大切です。
注意点としては、会社としての都合だけでなく、従業員のキャリア展望ややりがいを考慮することも大切ですので、面談で従業員に希望を聞いた上で、慎重に検討する必要があります。また、人どうしの相性や組み合わせもありますので、生産性向上だけのねらいに偏らないよう注意が必要です。
【ステップ5】従業員個人のスキルアップ
5つ目のステップは、従業員個人のスキルアップです。
従業員がスキルアップすれば、業務の量や質の向上につながります。会社が指定するスキルだけでなく、現場の従業員にもヒアリングし、意見を聞いてみましょう。「こういうスキル取得を支援してもらえると嬉しい」「同業他社の人から聞いたが、〇〇研修は受けた方がよさそうだ」といった回答が得られ、そこに重要なヒントがある場合があります。
スキルアップは、会社に関わるすべての従業員に、常に意識してほしいものです。会社としては、日頃からのスキルアップ意識の啓発や、スキルアップ内容の定期的なフォローに努めましょう。
【ステップ6】ツールの活用

6つ目のステップは、ツールの活用です。
近年は、DXやネット環境の普及、テレワークの広がりにより、さまざまなツールを気軽に利用することができるようになりました。自動化、ペーパーレス化、マニュアル作成ツール、コミュニケーション改善、知識や情報のスムーズな共有など、さまざまなツールがあります。これらを活用すると、さらなるコスト削減や業務改善に役立てることができます。
例えば、富士通ラーニングメディアが提供する「KnowledgeSh@re」は、業務マニュアルの作成・閲覧・共有のためのツールですが、これまでご紹介した生産性向上の施策のうち、以下の施策に活用できます。
- ステップ1の「現状業務の見える化」
(業務内容や流れを明確にし、端末があれば24時間いつでもどこでも業務を把握できる) - ステップ3の「アウトソーシングの検討」
(マニュアルをペーパーレス化し、印刷や保管、旧版廃棄などの手間をゼロにする) - ステップ5の「従業員個人のスキルアップ」
(全従業員のノウハウを集約した場所を作り、社員教育にも使用できる)
このツールは60日間無料体験ができますので、そういった無料体験を利用してサービス内容が自社にマッチしているか見極めるとよいでしょう。
マニュアル作成・共有ツール「KnowledgeSh@re」を60日間お試しいただけます。
『60日間無料で試してみる:KnowledgeSh@re無料トライアル』
まとめ
この記事では、生産性向上について、その定義や業務効率化との違いなどについて解説しました。
生産性とは、生産物と投入資源の割合です。生産性を向上することは、生産物をより多く生み出し、投入資源をより少なく抑えることであり、業務効率化とは、業務を見直してムリ・ムダ・ムラを改善することですので、業務効率化は生産性向上のための施策の1つであるといえます。
生産性向上を実現できると、従業員満足度や顧客満足度が上がり、より一層のコスト削減ができるメリットがあります。生産性向上のためには、以下の6つのステップを踏むことをご説明しました。
- 現状業務の見える化
- 業務の取捨選択
- アウトソーシングの検討
- 人材の再配置
- 従業員個人のスキルアップ
- ツールの活用
生産性向上は、企業活動において必須の課題であり、日本の国際的競争力を上げるためにも取り組んでいきたい課題です。ぜひ、自社に取り入れられそうな施策をさっそく実践してみてください。
富士通ラーニングメディアの「KnowledgeSh@re」
生産性向上にも、本格的なマニュアルを手軽に作成できる『KnowledgeSh@re(ナレッジシェア)』が役立ちます。どのようなツールなのか、60日間の無料体験で確認できます。
マニュアル作成・共有ツール「KnowledgeSh@re」を60日間お試しいただけます。
『KnowledgeSh@re無料トライアル』
※資料はこちら
関連記事:『作業効率の改善のために必要なポイントを徹底解説』
伝わるマニュアルで業務課題を解決「富士通ラーニングメディアのマニュアル作成・運用サービス」
「良いマニュアルってどうやって作るもの?」「もっと効率よくマニュアルを作成したいけどノウハウや⼈⼿が⾜りない…」と悩んでいませんか?
富⼠通ラーニングメディアでは、このようなお客様の声・ご要望をしっかりとお聴きし、マニュアルの利用者や用途・目的に合った、最適なマニュアルを作成いたします。
どんなことができるのか?詳しくはこちらから