業務効率化のツールを導入する目的から具体的な選定方法まで徹底解説

皆さんの職場では、働き方の変化を感じていますか?
近年は、働き方改革の流れで、長時間労働に頼らずに今まで以上の成果を上げることが求められています。また、少子高齢化に伴い2065年までに労働力人口が4割減少すると予想されています。
このような状況の中、生産性を向上していけるよう、業務効率化が必須の課題となってきました。業務効率化は、人の成長をうながすソフト面の仕組みと、業務を自動化などで効率化するハード面の仕組みをそろえるとうまく実現します。
昨今ではネットワーク環境の整備や技術の進歩にともない、こういった仕組みを構築する業務効率化ツールが数多く開発されています。
ツールを活用すれば、これまでの業務効率化よりも、よりスピーディに効率化を達成できます。そこで今回は、ツールを導入するメリットや選び方のポイント、ツールの種類をご紹介します。業務効率化の課題検討での参考にしていただければ幸いです。
- <業務マニュアルのクラウド移行を検討されている方におすすめ>
- どのマニュアルクラウドツールが自社に適したサービス
であるかを評価するポイントを
「SaaSサービスとして」「マニュアルクラウドツールとして」 - 『マニュアルクラウドツールを迷わず選定できる導入チェックポイント』
- ~これで迷わない!自社に最適なツールを導入する際に必見~
- 資料ダウンロード
2つの観点からご紹介しています。
業務効率化ツールを検討する目的
業務効率化ツールとは、業務を効率化してくれるツールのことで、次のような種類があります。
- コミュニケーションのツール
- タスクやプロジェクトのツール
- 定型作業の自動化のツール
- 顧客管理のツール
- ペーパーレス化のツール
こういったツールの活用を検討する目的は、大きく分けて3つあります。1つずつ見ていきましょう。
【目的1】「ムリ」「ムダ」「ムラ」を削減
業務におけるムリ・ムダ・ムラを削減する目的です。
業務やスケジュールにおけるムリ、資金や人材を必要以上に投下しているムダ、商品やサービスの品質が一定ではないムラがある状態などをなくすことです。これまで以上にムリ・ムダ・ムラを削減するためには、仕組みとしてのツールの導入が求められます。
【目的2】労働人口が減る中で求められる業務効率
労働人口が減る中で求められる業務効率化策を実施する目的です。
少子高齢化により、中長期的に働き手の人口が減少傾向にある中で、企業もその状態を想定して従業員数をコントロールした経営をしています。少ない人数でもこれまで以上に成果を挙げられる体制を作るために、業務効率化ツールの導入が有効となります。
【目的3】働き方改革、リモートワーク普及にともなうDX推進
働き方改革やリモートワーク普及によるDX推進が目的です。
働き方改革やコロナ禍の影響により、リモートワークが普及しました。リモートワークを実現するには、ネットワーク環境やリモートシステムを整備しなくてはならず、DX(デジタルトランスフォーメーション)が必須となりました。リモートワークにともない、マニュアルなどの社内資料閲覧や社内コミュニケーションにも、オンライン利用も可能な業務効率化ツールの導入が必要となってきます。
業務効率化ツールを導入するメリット
業務効率化ツールを導入すると、コスト削減、生産性向上、ワークライフバランスの向上などのメリットを得ることができます。
これらの3つのメリットについて、ご説明します。
【メリット1】コスト削減につながる
1つ目のメリットは、コスト削減につながることです。
業務を見直した結果、「この業務は自動化できる」とわかった箇所に自動化のツールを導入すると、人手のコストを省くことができます。ペーパーレス化のツールを導入することで、紙で印刷して顧客宛に送付していた資料をデータで閲覧できるようになり、紙のコストや人手のコストを削減できます。
業務効率化ツールを導入することで、業務のムダを削減することができ、コスト削減につながります。
【メリット2】生産性向上につながる
2つ目のメリットは、生産性向上につながることです。
生産性向上とは、少ないリソースで多くのアウトプットを生むことですが、業務効率化ツールの仕組みを活かすことで、一人当たりや単位時間当たりの生産量を増やすことができます。
例えば、データ入力をツールに任せることで、一人で1時間当たり100件だった作業が、人手を介さず1時間で数千件できるようになるなど、大きな効果を挙げられます。浮いた人手は新しい事業の調査や検討などの違う仕事ができるため、業務効率化ツールの導入は生産性の向上につながります。
【メリット3】ワークライフバランスの向上
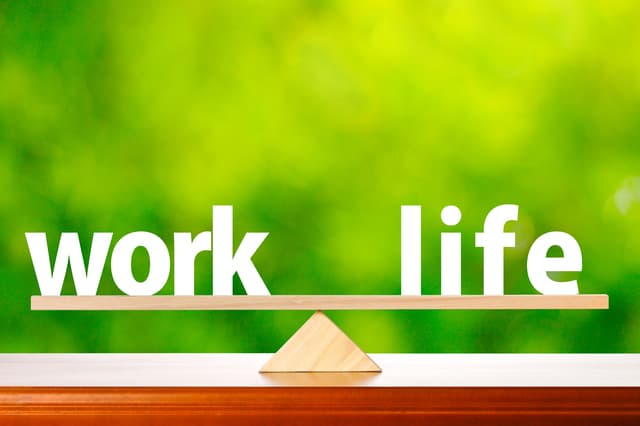
3つ目のメリットは、ワークライフバランスの向上です。
業務効率化ツールを活用して作業の時間を短縮したり、進捗状況を可視化したりすれば、時短勤務や有給取得もしやすくなり、従業員の私生活が充実し、仕事への意欲を高められます。
また、従業員のタスクをツールで共有すれば、もし従業員が急に休むなどしても代わりにサポートできる体制を作ることができるので、安心して自身や家族の体調管理を優先させられます。
業務効率化ツールを導入することで、従業員のワークライフバランスの向上につながります。
業務効率化ツールを選定するポイント
次に、どのような業務効率化ツールを選べばよいのか、選定するポイントを4つご紹介します。一番のポイントは「自社の課題を解決できるかどうか」です。そして、操作性やサポート体制などの使い勝手も重要です。
業務効率化ツールを選定する前に、ぜひこちらをご参照ください。
関連資料:『マニュアルクラウドツールを迷わず選定できる導入チェックポイント』~これで迷わない!自社に最適なツールを導入する際に必見~』
【ポイント1】自社の課題を解決できるものか
1つ目のポイントは、自社の課題を解決できるものかどうか、ということです。
業務効率化ツールを決定する前に、業務効率化が必要な対象業務を洗い出します。そして、検討しているツールが課題解決できるツールなのかどうかを確認します。
さらに、検討しているツールの機能や仕様をよく確認しましょう。業務効率化だけでなく販促も可能、自社の既存のシステムとつなげることが可能など、課題解決だけでなく、副次的効果をもたらしてくれる可能性もあります。
【ポイント2】操作性がよいか
2つ目のポイントは、操作性がよいかということです。
新しいツールを導入するとなると、従業員は操作を一から覚えることになります。画面が見やすく、手順がシンプルで操作性がよいと、これなら使っていけそうだと前向きな気持ちになれます。
ツールを実際に使用する従業員に試してもらってから、ツールを選定するとよいでしょう。
【ポイント3】フリープランの有無
3つ目のポイントは、フリープランの有無です。
例えば「30日間使い放題」「60日間無料」といったフリープランがあれば、効率化が図れるかどうか、操作がしやすいか、より確実に確かめることができます。
予算が限られている場合は、効果を確認してから導入する方が安心ですので、フリープランの有無を確認することをおすすめです。
例えば、このようなトライアルなら約2か月間ツールを試すことができます。
『60日間無料で試してみる:KnowledgeSh@re無料トライアル』
【ポイント4】サポート体制の有無

4つ目のポイントは、サポート体制の有無です。
社内にエンジニアがいて、外部の業務効率化ツールについても十分対応できるのであれば、ツールのサポート体制は不要ですが、もしエンジニアがいなくて使い方やトラブルの対応が難しい場合は、サポート体制があると心強いです。
初めて使用するツールは、既存のシステムとも親和するか未知数な部分がありますので、慎重に考えるとよいでしょう。
業務効率化ツールの種類
業務効率化ツールにはどんな種類があるのか、主なものを5つご紹介します。
職場の業務を効率化できそうなツールがあるか、イメージしながら読んでみてください。
コミュニケーションの効率化
従業員どうしのコミュニケーションを効率化するツールです。
業務に関する連絡や、従業員全員への周知にかかる時間が大幅に削減できるものです。
例えば、チャット機能、Web会議機能、スケジュール機能、掲示板機能のあるツールがあります。チャットへコメントがつけられるものや、チャット内の検索に優れたものもあり、従業員どうしのコミュニケーションを助けてくれます。
タスク・プロジェクト管理の効率化
タスク・プロジェクト管理を効率化するツールです。
タスクやプロジェクトの進捗状況や、コードやドキュメントのバージョンを把握でき、プロジェクトの情報を一元管理できるものです。
例えば、ガントチャート(横棒で作業の進捗状況を表す工程表)やフローチャート(図形と矢印で作業の流れを示す図)でタスクやプロジェクトの進捗を可視化し、現状どの工程にいるかをつかみやすいものがあります。情報管理しやすくなれば、情報共有や情報共有範囲のコントロールなどにも役立ちます。
定型作業の自動化
定型作業を自動化するツールです。
データ集計やメール送信、文書の送付など、定型化した作業を自動的に行うものです。手書きの文字を入力・確認・修正するツールや、給与や旅費交通費の計算チェックや精算を行うツールなど、さまざまなツールがあります。
人手を省くだけでなく、人によるミスもなくなり、ミスの対応の時間をも削減することが可能です。
顧客管理の効率化
顧客管理を効率化するツールです。
名刺のデータ化を中心に、顧客の属性情報や面談記録などを一元管理し、顧客情報の管理を効率化するものです。進捗中の案件管理もできる、営業支援も行えるツールもあります。
名刺をデータ化することで社内のペーパーレスにもつながりますし、面談記録などの情報からコンタクトをとるよう注意喚起するなど、マーケティングに役立つツールにもなります。
ペーパーレス化の促進
ペーパーレス化を促進するツールです。
例えば、見積書や請求書、契約書といった書類をデータのやり取りで完結させるツールや、ファイルの共有・検索力に優れたツールなどがあります。
ペーパーレスが進めば紙や印刷のコストや郵送代、朱肉代、紙の保管や廃棄のコストも削減できます。また、紙を誤って処分したり紛失したりすることを防ぎ、顧客情報の漏洩リスクを抑えられ、事務の堅確化にもつながります。
まとめ
従業員の働き方の変化により、職場の業務効率化が必須な状況になりつつあります。
業務効率化ツールを導入することで、ムリ・ムダ・ムラの削減やDX推進などの目的を達成することができます。そして、組織の生産性向上や従業員のワークライフバランスの向上につながるメリットがあることをご紹介しました。
業務効率化ツールには、次のようなものがあります。
- コミュニケーションのツール
- タスクやプロジェクトのツール
- 定型作業の自動化のツール
- 顧客管理のツール
- ペーパーレス化のツール
ツールを選ぶポイントは、まずは業務の課題を解決できるものかが重要です。その次に、操作性がよいか、フリープラン・サポート体制の有無、など、使い勝手も確認すべきポイントです。
まずは、職場や業務単位でスモールスタートしてみる、フリープランを活用し、実際に使用することになる従業員が操作してみて、効率化の効果がありそうか試してみる、といった方法をとると安心です。
マニュアル作成ツールをお試しいただけます。
『60日間無料で試してみる:KnowledgeSh@re無料トライアル』
関連記事:『マニュアル作成が成功する7つのコツ!実施ステップやツール選定のポイント・手順書との違いも解説』
富士通ラーニングメディアの「KnowledgeSh@re」
職場の業務効率化をすすめるならマニュアル作成ツール「KnowledgeSh@re(ナレッジシェア)」が役立ちます。
簡単な操作で本格的なマニュアルを作成できるツールです。どのようなツールなのか、60日間の無料体験で確認できます。
マニュアル作成・共有ツール『KnowledgeSh@re無料トライアル』
※資料はこちら
伝わるマニュアルで業務課題を解決「富士通ラーニングメディアのマニュアル作成・運用サービス」
「良いマニュアルってどうやって作るもの?」「もっと効率よくマニュアルを作成したいけどノウハウや⼈⼿が⾜りない…」と悩んでいませんか?
富⼠通ラーニングメディアでは、このようなお客様の声・ご要望をしっかりとお聴きし、マニュアルの利用者や用途・目的に合った、最適なマニュアルを作成いたします。
どんなことができるのか?詳しくはこちらから

