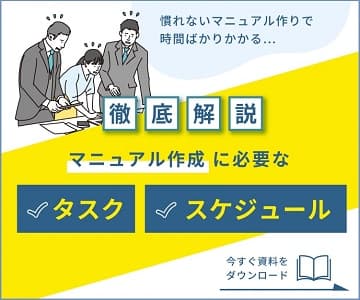マニュアルの意味は?企業が取り組むべき理由を詳しく解説
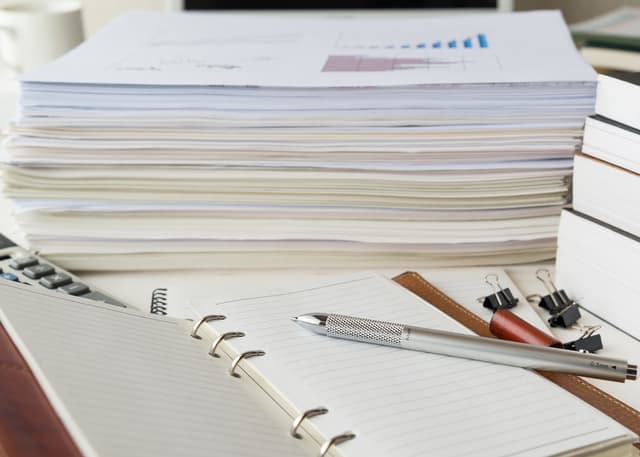
マニュアルの運用や管理に失敗したくない、とマニュアルの意味について改めて考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ニューノーマルな働き方で従来の常識が通じなくなりつつある昨今において、マニュアルの運用を失敗しないためにもマニュアルの意味を正しく理解しておくことが大切と言えます。
今回はマニュアルの意味や狙い・メリットについてわかりやすく紹介していきます。
マニュアルの意味とは
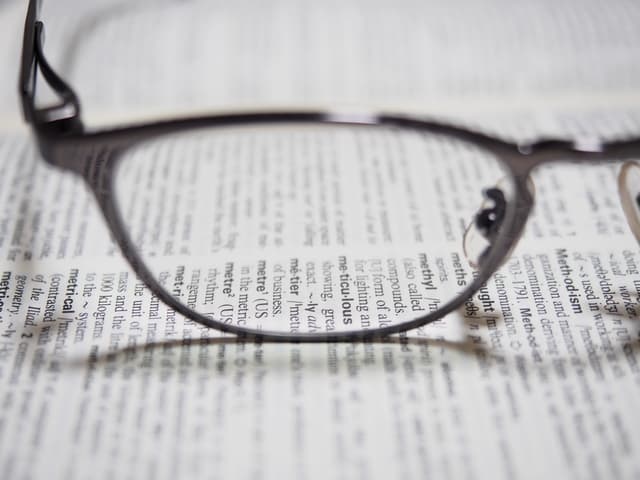
マニュアルにはどのような意味があるのでしょうか。以下の4つの観点から解説していきます。
- マニュアルが持つ意味
- 手順書との違い
- ハンドブック、取扱説明書、手引きとの違い
- 業務マニュアルと操作マニュアルの違い
一つずつ詳しく見ていきましょう。
マニュアルが持つ意味
最初に、マニュアルが持つ意味について考えて行きましょう。
マニュアルとは、従業員全員が同じレベルで業務を遂行し、一定の結果を出す為に業務手順やルールなどをまとめたドキュメントです。
例えば、仕事で使う業務マニュアルがあります。業務マニュアルには全体の業務フローと目指すべきゴール、具体的な手順、前提条件、注意事項、必要な知識などの内容が書かれています。
マニュアルに書いてある内容通りに手順を進めることで、従業員全体の作業品質やスピードの一定化を図ることができます。
手順書との違い
マニュアルをさらに理解するために、マニュアルと手順書との違いをチェックしましょう。
マニュアルと手順書はとてもよく似ているため混同されがちです。どちらにも作業を進めるための手順が記されています。違いとしては取り扱う範囲の大きさが異なることが挙げられます。
マニュアルは、手順書に比べて範囲が大きい言葉として使われるケースが多いと言えます。
例えば、業務の全体イメージ・業務フローを前提とした上で、ステップ毎の作業手順を詳しく書いてあります。
また、実施する上で必要なノウハウや、誰に何を依頼すべきか補足事項についても書いてあり、内容が盛りだくさんです。
一方で、手順書は小さな範囲で利用されるケースが多い言葉で、特定の業務や工程等の作業手順など、個人で完結できる範囲の流れがまとめられています。
例えば、手順書の通りに実施することで、ソフトウェアの設定等を問題なく完了できるといった内容です。
手順書にはマニュアルと違って業務全体のフローが書かれていないものが多く、マニュアルの一部内容を抜粋して手順書としてまとめることもあります。
ハンドブック・取扱説明書・手引きとの違い
マニュアルと似ている言葉に、ハンドブック・取扱説明書・手引きがありますが、それらの言葉とマニュアルの違いも整理してみましょう。
- ハンドブック
ハンドブックは、特定の分野において頻繁に使うであろう項目や、重要事項を簡潔にまとめたドキュメントです。
業務に必要な物事の扱い方、ソフトウェア操作方法などが書かれています。一般的なものとして、防災ハンドブックなどがあります。コンパクトなサイズが多く、マニュアルの一部をハンドブックとしてまとめておくことで、持ち運びに便利になります。
マニュアルとハンドブックの違いとして特にボリューム感が違っており、ハンドブックは持ち運びできる必要最低限の範囲に絞って作成されることが多いと言えます。 - 取扱説明書
取扱説明書は、機械やソフトウェア等について使用方法、操作手順を説明したドキュメントです。
業務全体のイメージやフローについて書かれているマニュアルに対し、取扱説明書は個々の機器の仕様や操作方法に限定して書かれています。
マニュアル記載の必要な機器に関して、取扱説明書を参照して一部の確認を行うというケースもあります。 - 手引き
手引きとは、業務手順が書かれたドキュメントのことを指します。
マニュアルは従業員全員が同じ結果を出すためにしっかりと作業内容が指定されているのに対して、手引きには大まかな方向性ややり方について書かれているというケースが多いと言えます。
手引きでは、具体的な手順は従業員自身が決めていくため、マニュアルに比べると従業員が実施したアウトプットがそれぞれ異なる可能性が高くなります。
業務マニュアルと操作マニュアルの違い
最後に、業務マニュアルと操作マニュアルの違いについて説明します。
マニュアルには複数の種類があり、それぞれの違いを知ることで作成・運用を適切に対応することができます。
- 業務マニュアル
業務マニュアルは業務の全体イメージやフローに加えて、実際の手順について詳しく書きます。
また、業務単位でマニュアルを作成することで、業務ごとに実施が必要な社内教育をスムーズに行うことができます。
業務マニュアルは、企業の組織変更や業務内容の変化に大きく影響されますので、基本的に更新頻度が高い傾向です。 - 操作マニュアル
操作マニュアルは、業務システムなど操作する際の手順が中心に書かれています。
例えば、営業管理システムのマニュアルには、ログイン方法・操作方法・問い合わせ先などについて書きます。業務マニュアルに記載の一部を操作マニュアルとしておこすこともあります。
操作マニュアルは、システムが置き換わったり、機能が追加された時などにの更新するドキュメントなので、業務マニュアルに比べると更新頻度が低いことが多いと言えます。
企業がマニュアル作成を進める意味と狙い
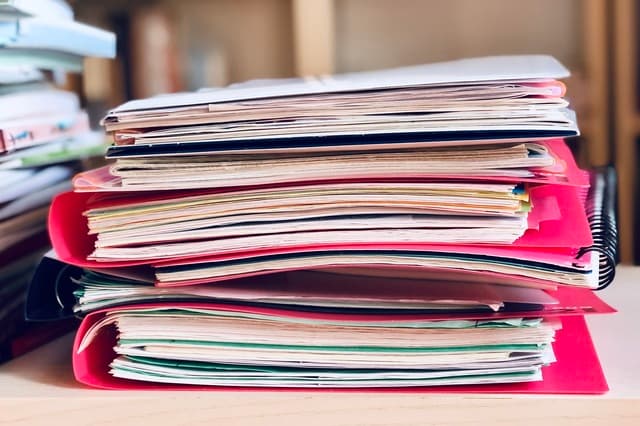
多くの企業がマニュアルの作成を進める目的として、以下の3つがあります。
- 業務の標準化
- 全体の業務遂行レベルの向上
- 属人化の回避
一つずつ詳しく見ていきましょう。
関連記事:『マニュアル作成が成功する7つのコツ!実施ステップやツール選定のポイント・手順書との違いも解説』
業務の標準化
1つ目の狙いは、業務標準化です。マニュアルを作成することで業務を整理・必要な手順を明確に示すことができ、従業員に徹底させることが可能になります。
従業員が業務を遂行する際、マニュアルがないと自分自身で手順を決めて実施する必要があります。
そのような場合、考えて作業する分無駄も多くなり、最終的なアウトプットの品質もバラバラになってしまいます。
マニュアルによって誰もが迷わずに、一定のレベルで業務を行えるようになりますし、業務を標準化できることで企業としての生産性を向上することができます。
全体の業務遂行レベルの向上
2つ目の狙いは、全体の業務遂行レベルの向上です。マニュアルを活用すれば、従業員による業務品質のバラつきを防ぐことが可能です。
従業員それぞれが自分の進め方で作業をすると、その過程で作業ミスが発生してしまったり、無駄に多くのリソースを使ってしまう可能性があります。
マニュアルに業務に必要な手順を簡潔に記載することで、従業員が迷わずに正確な作業を進めることができるようになり、全体の業務遂行レベルを合わせることができます。
属人化の回避
3つ目の狙いは、属人化の回避です。マニュアルがあれば全員が同じように実施でき、同じ結果を出すことが可能なため、従業員個人に業務が偏ることが少なくなります。
特定の業務に習熟した従業員に、その仕事ばかりさせた結果、その従業員以外はその仕事の進め方がわからない、という状況に陥ってしまうことがあります。
または、普段は発生しない業務が発生した「いざ」と言う時に、どこに対応方法がまとめてあるのか分からないため、いつも古参の従業員に確認するといったケースもあります。
マニュアルには業務に必要な知識が全て詰まっているため、手順を順に従って進めることで、上記悩みを解決できます。
業務のノウハウを言語化し、マニュアルに落とし込むことで、特定の人に依存した状況から抜けることができます。
また、ITツールを活用するなど検索性を高めることで、必要な時に人に確認しないで必要な情報を得ることができるようになります。
まとめ
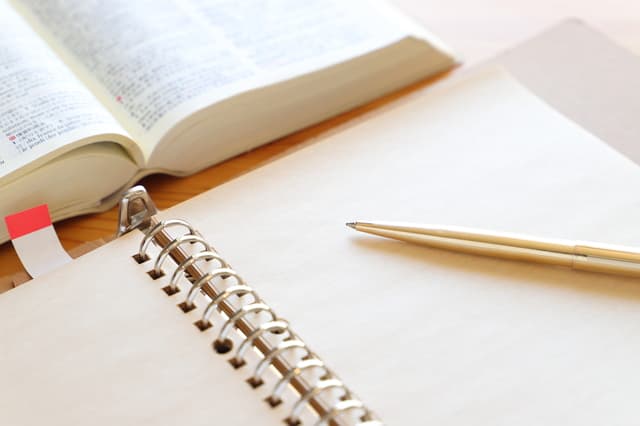
マニュアルの意味と狙いを本記事で詳しく解説しました。マニュアル化することによって業務効率化を行うとともに、品質の向上や属人化の回避をすることができます。
マニュアル化をすすめるにあたっては、マニュアル作成ツールの活用がおすすめです。フォーマットの整ったITツールを活用することで高品質なマニュアルを効率よく作ることが可能です。また、従業員がマニュアルをいつでも簡単に検索できるなど運用効果を高めることができます。
マニュアル化の意義を高めるために、マニュアル作成ツールの活用も検討しましょう。
富士通ラーニングメディアの「KnowledgeSh@re」
マニュアル化をすすめるにはKnowledgeSh@re(ナレッジシェア)が役立ちます。どのようなツールなのか、60日間の無料体験で確認できます。
マニュアル作成・共有ツール『KnowledgeSh@re無料トライアル』
※資料はこちら