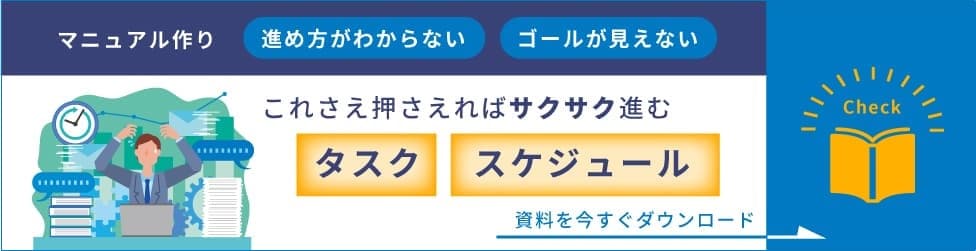作業ミスの再発防止策とは?メリット・必要な背景・具体策について詳しく解説!

人間は、何かしらミスをする生き物です。これまでの人生で「何もミスしたことがない」という人はほとんどいないでしょう。
ただ、仕事の場で作業ミスが発生してしまうと、生産性の低下や取引先からの信頼の失墜など影響が大きくなるため、再度ミスが発生しないよう、業務体制や仕組みを整備して再発防止策を講じる必要があります。
今回は、作業ミスの再発防止を行うメリットや、再発防止策が必要となる背景をご紹介し、具体的な再発防止策を8つ解説します。作業ミスが起きる原因や背景、作業ミスを発生させない具体策を知りたいとお考えの方に、参考にしていただければ幸いです。
作業ミスの再発防止策とは?
作業ミスの再発防止策とは、作業ミスが発生した際に作業の手順や内容を見直し、ミスが発生した原因や背景を突き止め、再度発生させないような対策のことです。
作業ミスが起きるのは、たまたまその担当者が不慣れだった、不注意だったと考えられがちですが、実は役割分担やコミュニケーションが不十分、ミスを防止する業務上の仕組みがない、といった組織の課題が背景にあり、そのような体制では誰でも作業ミスをしてしまう可能性をはらんでいます。
ミスは起こるものだという前提に立ち、さまざまな対策を立てて防止します。それでも想定外の作業ミスが起きてしまったら、二度と発生させないよう、また次の再発防止策を講じていきましょう。
作業ミスの再発防止策を行うメリット
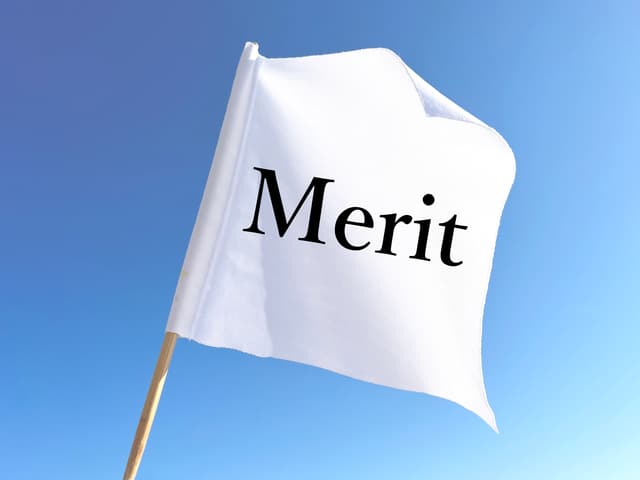
発生した作業ミスを、二度と発生させないための再発防止策を講じると、次のようなメリットがあります。
- 生産性向上
- 品質向上
- コスト削減
どのようなメリットか見ていきましょう。
生産性向上
起きてしまった作業ミスを再発させないよう防止策を実行し、現在の作業内容やフロー、手順などを改良することで、作業の堅確性や効率性が改善されます。
これから先の将来にわたってミスが起こる分の修正などの手間を未然に防ぎ、その分の手間で多くの製品やサービスを生み出し、生産性を向上させることができます。
品質向上

作業ミスの再発を防止することによって、作業担当者によるミス数のばらつきをなくし、合格基準ぎりぎりの製品を減らし製品の品質を向上させることができます。
顧客や取引先からのクレームを未然に防ぐとともに、不良品が少なくむしろ品質がよくなることで顧客ロイヤルティの向上も期待できるようになります。
コスト削減
作業ミスの再発を防止すると、不良品のやり直しによって再投入した材料や、修正対応にかかっていた時間や手間など、ムダなコストをかけずに済むようになります。
その分のコストを、生産量増加や新商品の開発、製造機器の改善などに充てることができ、さらなるコスト削減や売上拡大につなげていくことができます。
作業ミスの再発防止策が必要となる背景
作業ミスの再発防止策が必要となる背景には、次のようなものがあります。
- 不明確な作業手順や指示
- 疲労やストレス
- 不適切な資源やツールの使用
- 不適切なコミュニケーション
- スキルや知識の不足
- 過信や自己確認の不足
- 注意力の欠如
- リスク放置
一つずつご説明します。
1.不明確な作業手順や指示
作業手順や指示が不明確だと、作業ミスが発生しやすくなります。
作業手順があいまいで、誰がどこまで行うのか、どのレベルまで行うのかが不明確だと、新人や転入したての担当者は自分の考えだけで行動してしまい、ミスが生じてしまいます。
また、作業の途中で他の担当者から連絡をもらう必要があったり、逆にこちらから計数の報告をしなければならなかったりする場合に、どの担当者とやり取りすべきかの指示が不明確だと、作業ミスにつながります。
このような場合は、作業手順や指示を適切に共有する体制を整える必要があります。
2.注意力の欠如

作業への集中を妨げる要因が存在していると、作業ミスが発生しやすくなります。
例えば通常は行われない工事の騒音が気になってしまったり、作業の後工程を心配していたりすると、注意が散漫になってしまい、作業ミスが発生してしまいます。
このような場合は、どの工程まで作業が進んでいるのか、通常より進捗に遅れが見られないかなどを常にチェックできるようにし、注意力の欠如が起きていることに早く気づいて対処するのが大切です。
3.過信による自己確認の不足
作業者が自分のスキルを過信してしまい、確認がおろそかになると作業ミスが発生しやすくなります。
自分の技術やスキルに自信や慣れによる油断があるばかりに、作業後にきちんと確認せず完了させてしまうことで作業ミスが発生します。
このような場合は、自己確認だけでなく、他の担当者による確認も行う体制にするとよいでしょう。
4.疲労やストレス

一見、個人の能力や体力に起因するように見えますが、これも元をたどれば疲労を抱えやすい勤務シフトや労働環境が背景にあります。
疲労やストレスがたまると、気力が充実しているときのような集中力や粘り強さが失われがちになり、作業ミスが発生しやすくなります。
このような場合は、勤務シフトや作業工程を見直し、過度な負荷のない体制への改善が望ましいでしょう。
5.スキルや知識の不足
作業に必要となるスキルや知識について、適切な教育やトレーニングが行われていないことで、作業ミスが発生しやすくなります。
新人だけでなく、職場に転入したばかりの他業務経験者も、必要なスキルや知識が不足していることがあります。その確認をせずに「ベテラン従業員だから」とばかりにいきなり大きな作業を任せてしまい、作業ミスが発生してしまうことがあります。
このような場合は、作業する担当者のレベルに応じて、適切な教育やトレーニングを行う必要があります。
6.不適切な資源やツールの使用

業務において、適切でない資源やツールを使用してしまうと、作業ミスが発生しやすくなります。
材料、機器や機械、システムやツールなど作業に必要なものの中で、不適切なものが混ざっていると、作業ミスが発生してしまいます。
このような場合は、まずミスの原因を突き止め、不適切な部分を早急に是正しましょう。そしてその原因が起こる背景を分析します。例えば、担当者が材料の計量を誤ったことが原因であれば、その背景に原材料の配合変更があった、といった具合です。
7.不適切なコミュニケーション
コミュニケーションがうまくいっていないことで、作業ミスが発生しやすくなります。
聞き手が必要な情報を聞いていなかったり、話し手が伝え聞いたけれども誤解してしまう言い方だったりといったコミュニケーション不足があると、作業ミスが発生してしまいます。
このような場合は、必ず復唱する、口頭ではなく文面でやり取りするなど、コミュニケーションの方法やツールを見直し、改善していくことが求められます。
8.リスク放置
リスクがあることに気づいていながら、必要な対処をせず放置していると、作業ミスが発生しやすくなります。
例えば、一人の担当者が仕事を抱え込み属人化している状態では、周囲の人が細部まで把握していないため、その人が不在の際は作業ミスが発生してしまい、納期が遅れるなどのリスクがあります。
このような場合は、リスクを放置せず、必要な予防策を講じるよう行動をとれる体制を敷く必要があります。
作業ミスの再発防止策
作業ミスの再発を防止する、具体的な方法を8つご紹介します。
- マニュアルを作成する
- チェックリストを使用する
- 二重チェックを実施する
- プロセス改善と標準化をはかる
- 教育とトレーニングを実施する
- ミスの原因を徹底分析する
- コミュニケーションを促進する
- リスク管理を強化する
ご自身の職場でまだ実施していない方法があれば、ぜひ取り組んでみてください。
1.マニュアルを作成する

作業内容や手順をまとめたマニュアルを作成します。
一つの作業に対して、担当者の経験やキャリアによって「ここは確認すべきだ」「ここは細かく確認しなくてよい」などと判断基準の見解にばらつきが出ます。そういうときに統一見解に基づいたマニュアルがあれば、同じ判断基準に基づいて作業を行うことができ、作業手順や指示が明確になり、作業ミスを防止できます。
そして、マニュアルは一度作成したら終わりではなく、作業に変更点が生じたら都度変更を反映させ、変更後マニュアルを担当者間で共有すること、迷うことがあればマニュアルに戻ることなどを周知徹底すると、さらに組織全体の作業品質が向上していきます。
2.チェックリストを使用する
作業手順やレベル、確認項目をまとめたチェックリストを作成し、作業する際に必ず使用します。
例えば、「誰が」「どこで」「どのレベルまで」「何をやるか」を時系列にまとめた表を作成し、今の手順をチェックしてから次の手順に行く、といったチェックリストにします。チェックリスト作成とともに、作業終了後はチェックリストを作業後の成果物などと一緒にマネージャーに提出する、といったフローも確立すると、注意力の欠如などによる作業ミス防止につながります。
チェックリストの作成については、次の記事を参考にしてみてください。
関連記事:『マニュアル定着化に役立つチェックリストとは?メリット・デメリットと作成方法を解説』
3.二重チェックを実施する

担当者が作業を完了したら、別の担当者がチェックする「二重チェック体制」にします。
例えば、作業ごとに作業者とチェック者を決める、グループの中で互いにチェックし合うなどの体制を決めます。重要な手順では、さらに上司など三人目のチェック者を設けてもよいでしょう。この体制が整うと、自分のスキルを過信し自己確認を怠ることによる作業ミスを防止できます。
ポイントとしては、最初に作業した担当者も、別の担当者に見せる前に自分で最終チェックを行うことです。そうでないと「二重」のチェックになりませんから、作業をやりっぱなしではなく自己チェックを行いましょう。同時に、2回目のチェックを行う担当者も「この担当者はベテランだから大丈夫」などと過信せず、きちんとチェックを行うことも大切です。
4.プロセス改善と標準化をはかる
作業のプロセスの改善や、標準化をはかります。
作業プロセスの標準化とは、その作業に携わる人が誰であっても同じ成果物を生み出せるように、プロセスを共有することです。作業の手順や作業内容を見直し、安全で生産性の高い工程へと改善します。必要な人員数が不足しているようであればシフトの見直しも行います。これによって、疲労やストレスによる作業ミスが削減できます。
標準化については、次の記事もぜひご覧ください。
関連記事:『業務標準化とは何か?実現のための5つのステップを解説』
5.教育やトレーニングを実施する

作業ミスが発生したら、教育やトレーニング内容を見直し、実施します。
作業する担当者の経験値や習熟レベルに応じて、事前にスキルや知識の研修を行います。さらに作業場でOJT指導を行ったり、シミュレーションできる機械でトレーニングしたりするなど、求めるスキルや知識を担当者が身につけられるようにします。
これによって、スキルや知識が不足したことによる作業ミスを削減することにつながります。
6.ミスの直接の原因や背景を徹底分析する
さまざまな再発防止策を講じても、なお作業ミスが発生するケースがあります。
作業ミスが発生した際は原因と背景を徹底分析することを職場で意識づけし、分析のフローややり方を策定しておきましょう。例えば、トヨタ自動車の生産現場から生まれた「なぜなぜ分析」のように、「なぜ起きたのか」を5段階ほどに分けて掘り下げるなど、やり方を決めておきます。いざ作業ミスが発生した際にスムーズに分析にとりかかることができます。
原因を徹底分析することで、作業ミスの原因を的確にあぶり出し、不適切な資源による作業ミスを防ぐことができます。
7.コミュニケーションを促進する

コミュニケーションの質を高め、できるだけ量を増やすよう促進します。
物事の捉え方は、同じ職場にいて同じ作業をしていても、人によって違う捉え方をしていることがあります。
例えば「余計なお世話と思われるかな」と遠慮せずに、「今のメールは〇〇をする、という意味ですよね」と確認し合ったり、作業が完了したら細かなことでも報告したりするよう心がけ、情報共有や意思疎通を徹底します。また、コミュニケーション量を増やすためには、社内コミュニケーションツールを導入するなどの方法もあります。
コミュニケーションの促進によって、コミュニケーション不足による作業ミスを減らすことができます。
8.リスク管理を強化する
リスクのおそれがある場合は明らかにし、速やかに対応するよう、リスク管理を強化します。
リスク管理の強化には、専門部署の設置が効果的です。例えば担当者が作業をしていて気づいたリスクについては必要な予防策を考え、すぐ実行に移せるものは実施しますが、リスク管理部署の分析の結果他の部署にも関わる大きなリスクが潜んでいることが判明すれば、リスク管理部署が横断的に対応を指揮します。
リスク管理の強化によって、リスクを放置してしまうことによる作業ミスを防止することができます。
お役立ち資料:『業務マニュアルをクラウド化するメリットとは?~業務マニュアルクラウドツールをお悩みの方は必見!~』
まとめ
今回は、作業ミスが発生した際に、再発防止策を考えることのメリットやその背景、具体的な再発防止策を8つご紹介しました。
作業ミスは、担当者の判断ミスなどのヒューマンエラーだと見なしてしまいがちですが、原因を調査すると、標準化された手順が担当者間で浸透していなかったり、ミスが起こってしまう体制であったりと、作業場の体制や仕組みに関する課題が背景にあります。ご紹介した再発防止策のうちまだ実施していない方法があれば、ぜひ実践してみてください。
特に、マニュアルは一度作成すると、長期にわたって作業ミスを防止する施策となります。チェックリストや教育・トレーニングにもそのまま活用できますし、プロセスの改善や標準化した手順の共有にも活用できます。
マニュアルを手間なく完成させることのできる「マニュアル作成ツール」では、どのような機能があるのか、こちらの資料で確認できますのでぜひご覧ください。
お役立ち資料:『KnowledgeSh@reのご紹介パンフレット (PDF:1,086KB)』
富士通ラーニングメディアの「KnowledgeSh@re」
作業ミスの再発防止策にもKnowledgeSh@re(ナレッジシェア)が役立ちます。
本格的なマニュアルが手軽に作成でき、品質のばらつきも削減できます。どのようなツールなのか、60日間の無料体験で確認できます。
マニュアル作成・共有ツール『KnowledgeSh@re無料トライアル』
※資料はこちら
伝わるマニュアルで業務課題を解決「富士通ラーニングメディアのマニュアル作成・運用サービス」
「良いマニュアルってどうやって作るもの?」「もっと効率よくマニュアルを作成したいけどノウハウや⼈⼿が⾜りない…」と悩んでいませんか?
富⼠通ラーニングメディアでは、このようなお客様の声・ご要望をしっかりとお聴きし、マニュアルの利用者や用途・目的に合った、最適なマニュアルを作成いたします。
どんなことができるのか?詳しくはこちらから